REPORTS
- レクチャー
「サウンドスケープ入門」
中川真
2021年7月18日(日) 13:00–14:30
CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
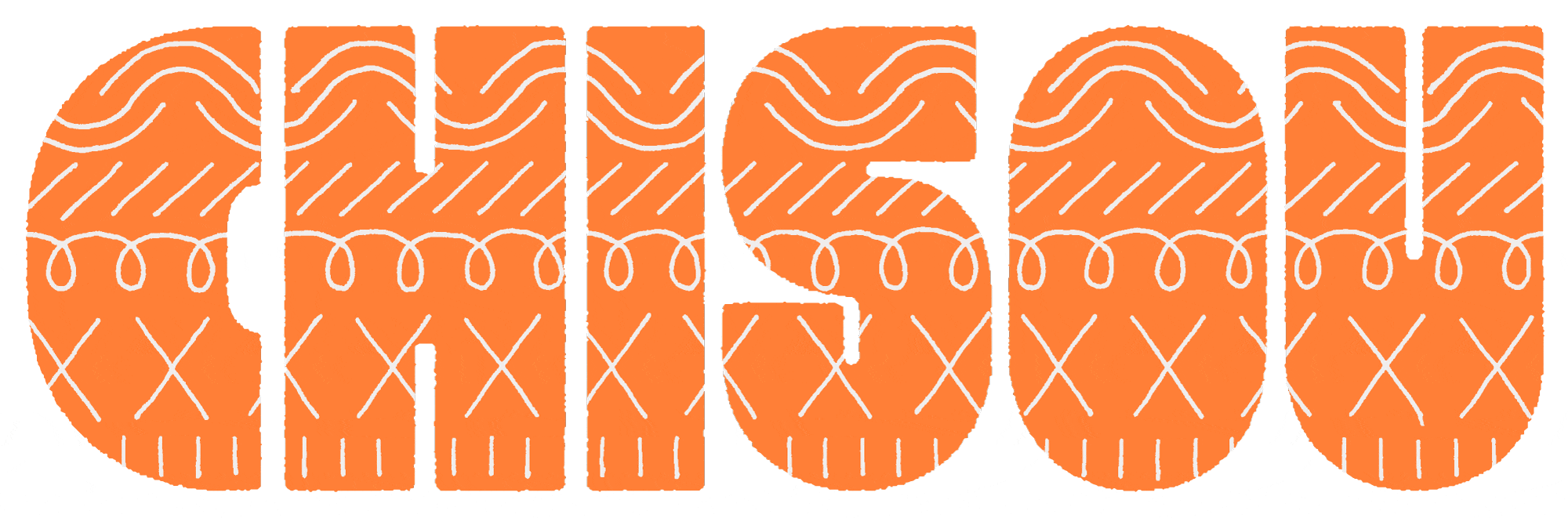
REPORTS
2021年7月18日(日) 13:00–14:30
CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

サウンドアートやコミュニティアートなど幅広い分野でユニークな研究活動を続けている音楽学者の中川真さんによるサウンドスケープ入門のレクチャーを実施しました。プログラム1「感覚」のキーワードである「聴く」ということの根源的な意味について、また、音を通して世界の捉え方や身体のあり方が変容していくことについて、これから考えを巡らしていくための重要な知識とアイデアが得られる時間になりました。
CONTENTS
「聴く」という字の原型は、中国古代の象形文字に遡ります。「聴」と「聞」という二つの字がありますが、もとになる字はパーツの形がすごく似ています。二つの字はもともと一緒だったのですが、ある時に分かれて二つの字になり、現代では我々も若干使い分けています。私は象形文字が大好きでして、形がすごくシンプル。「聴」の字には人間のパーツが含まれており、一生懸命に人間が音を掴もうとセンサーを広げている姿が表されています。
この「聴く」という字の根源的な意味は何なのかについて考えてみましょう。色々な物音を聴くということが思い浮かびますが、この字に表される人間はどんな音を聴こうとしていたのでしょうか。この字にはパラボラアンテナのような形が含まれていますが、この人間が聴いているのは一体何なのでしょうか。
実は、この人が聴いているのは、天にいるカミの声です。いわゆる宇宙を統括しているような超越した存在で、その声をキャッチしようとしている。漢字学者の白川静の解釈によると、祭事と関係する字と共通するパーツがたくさん使われているので、「聴」という字の原点は神様との関わりが非常に強いことがわかります。
しかし、カミの声って聴こえるものでしょうか。なかなか聴こえないですよね。ものすごい努力や集中力が必要だし、頑張っても聴こえないかもしれない。どれくらいの距離かわかりませんが、ものすごく遠いところですよね。漢字圏の人々にとって「聴く」という行為は、すごく遠いところの、聴こえるか聴こえないかわからない小さな音をキャッチすることであったということが伺えます。
そのような聴き方を、現代の我々はしているでしょうか。せいぜい数百メートル圏内の音を聴くぐらいですよね。「聴く」という行為がそもそも持っていた意味から、我々はかなり遠いところにいます。「聴く」という言葉を使う時には、ものすごく遠いところの小さな音に耳を澄ますことが原点なのだと、まず認識してください。
これから皆さんは、一連のフィールドワークを通して、耳や身体を変えていくことになります。そんなにセンシティブな耳になったら気が狂うのではと思い、我々は耳にフィルターをかけて何とかサバイブしてきたので、いきなり古代人の耳を持つと気が狂うかもしれない。だから、スイッチのオンオフの切り替えができるような身体にしていくことが大事ではないかと思います。

20世紀前半、ハンガリーにバルトーク・ベーラとコダーイ・ゾルターンという有名な作曲家がいました。ウィーンやパリなどのヨーロッパの中心から少し離れたハンガリーで、オリジナルなクラシック音楽をつくろうと、彼らはハンガリーの村々を訪れ、民謡を録音して回りました。その録音した音からアイデアを得て、すごく面白い音楽作品をつくりました。およそ90年が経ってから、私も同じ村を訪れて、「昔、バルトークという偉い作曲家が来ましたよね」と話しかけても、誰一人覚えていない。村には言い伝えも何も残っておらず、皆が「知らない」と答えるのです。
そのような中、ある村を訪れた時に面白い話を聞きました。村人全員で1年に1回だけ集まり、ある丘の上に登って、空を仰ぎ天の声を聴くのだと。その辺りではキリスト教が信仰されていたのですが、丘に登って天の声を聴くこととキリスト教は関係がなく、その村に代々伝わっていた神様との関係でした。キリストはもっと身近にいるけれど、ずっと向こうの方にいる神様の声を1年に1回聴くとのこと。あながち古代の中国だけの話ではなく、現代でもそのようなことをしている人たちがいるのですね。
私は奈良県大和高田市で生まれました。祖父が寺の住職で、小さい頃に不思議なことがありました。祖父が突然、袈裟のような着物を着始めて座敷で座っていると、トントンと木戸を叩く音がして、「村で誰々が亡くなったので来てください」と言われる。「わかった、わかった」と祖父は答えて出かけるのです。そういうことが何回もあったのですが、子どもながらに「順番がおかしいのでは」と不思議でした。木戸が叩かれて「誰かが亡くなった」と聞いてから、慌てて着物を着て出かけるのが必然的な流れなのに、なぜ祖父はその前に着替えているのか。祖父に尋ねると、「その時になったら村からざわざわと声が聴こえてくるから着替えるのだ」と。普通は子どもの方が圧倒的に聴覚が良いのですが、私には全然聴こえない。子どもに聴こえないのに祖父は聴こえる。そのやりとりに関して、村の人も何も不思議に思っていないのです。
今思うと、祖父の耳は、先ほどの「聴」の字の人間にかなり近かったのでしょう。普通では聴こえないような声に、祖父はずっと耳を澄ましていました。子どもだった私は、「どこそこの誰それさんが危ない」とか意識がなく、全く耳を澄ましていなかったけど、祖父は耳を澄ましていたから、村の中で何かあった時にすぐわかったのです。
祖父は耳の聴こえが良すぎて、自分が亡くなる前に横になっていると、遠くの道を歩いている村の人々が「あのお寺のおじいさん、もう亡くなるね」と話しているのが全部聴こえてきたと嘆いていました。そのような人がかつては当たり前のように存在していましたが、近頃は耳の感覚が急速に落ちてきているようです。
『日本書記』には、飛鳥時代に伊豆諸島で海底火山の爆発が起きた時のことが書かれています。太鼓みたいなドーンという音が、奈良の飛鳥でも聴こえたと記述されていますが、これは歴史的にも正しいと証明されています。桜島の火山についても、奈良時代に平城京で聴こえたという記述が残っています。かなり離れた場所からの音が、当時の人々には聴こえていました。
また、約30年前に昭和から平成に変わる時、鳴物停止の令が出されました。各音曲を3日間止めるように政府から命じられて、日本中が静かに慎みました。平成から令和に変わる時には、天皇が亡くならなかったため、鳴物停止の令は出ませんでした。音には火山の爆発など自然の音だけではなく、人間が発する音もあり、それならコントロールできる。音の鳴る領域まで権力が制することによって、人々を支配していたという社会的な出来事です。
江戸時代後期に、仙洞御所で後桜町天皇が亡くなった時は、御触れが出ました。町触というのは法令のようなもので、京都の町触を集めた資料集が京都町触集成なのですが、その中に「鳴物普請停止に候」と書かれている。鳴物とは音楽のことで、三味線や路上での音楽、パフォーマンスを止めなさいと。普請とは建物の工事のことで、それらを全て止めなければならない。普請は途中で解除されたのですが、鳴物は2カ月間停止、さらに魚屋も商売を3日間止めるように命じられました。天皇が亡くなった時に最も忌み嫌われたのが音でした。
天皇が亡くなり新しい天皇に変わる大嘗祭では、寺々は鐘や音を仏事で鳴らしてはいけないとされましたが、火事が起きた時だけは鐘を鳴らしても良いと言われました。地理的にすごく広い範囲で静寂が求められたのですが、まさに音によって人々をコントロールしてきた歴史があるのです。このように歴史資料の中には、空間的かつ時間的な問題が様々に交差している音の地層を読み取ることができます。
今日は「聴く」ことについて、いくつかの観点からお話ししていきますので、皆さんには「聴く」とは一体何なのかを自分なりに考えていただきたいと思っています。そのために、まず「測る」という観点から「聴く」ことについて考えてみましょう。測るというのは、自分と対象との関係を明らかにすること、例えば5メートル先に何かがあるとか、あるいは自分が今どういうところに立っているのかということを認識することですよね。音を通して世界を測ってみることが、「聴く」ということなのではないでしょうか。

ロバート・フラッドが描いた「天球の音楽」という絵があります。ギリシャ時代にピタゴラスが書いた宇宙と数と音の世界を表していますが、まるで地球のような形をしています。当時は天動説が信じられており、宇宙も同じような形をしています。ギリシャ時代の人々は、宇宙には数理的にすごく合理的な法則があると考えていました。太陽や月など色々な星がぶつかることもなく非常にうまく動いていることを、数によって合理的に説明しようしていました。そして、音の世界も非常に数理的に説明することができるということに、ピタゴラスは気づいたのです。
一本のピンと張った糸を弾くと、一定のピッチで音が鳴ります。それを半分にすると、完全に1オクターブ上の音になります。これを3対2にすると短い方はソの音になり、長い方はドの音になります。4対3にすると短い方はファの音で、長い方はドの音になります。1対2、2対3、3対4という非常にシンプルな張り方によって、4度とか3度とか5度になり、半音などになることをピタゴラスは発見したのです。
音の世界のように宇宙も振動していると考えて図に描かれたのが、「天球の音楽」です。この絵は、宇宙が素晴らしい音を立てて響いている姿なのです。素晴らしい音が響いている故に、宇宙は完全に調和しています。その後、哲学者は皆「聴こえない」とすごく悩んだらしいのですが、それ以降もケプラーや様々な学者が、惑星とメロディの関係や宇宙と音の関係について思索してきました。彼らは音が宇宙を捉える物差しだと考えて、音によって空間を測ろうとしていました。
江戸時代の医者であり農学者であり革命家でもあった安藤昌益は、音によって季節の変化、すなわち1年の周期を測っていました。彼の書物を読むと、雪中で鳴くキジの声や、雌を愛する鶏の声を聴いて、冬から春に変化していくことを知ったり、中春になって鳴る雷の音の変化でツバメがやってくることを知ったり、モズが始めて鳴くのを聞いて中夏であることを知るなど、自然の様々な音を聴いて季節の変化を知る様子が描かれています。安藤昌益は中国の『礼記』の思想を下敷きに、日本の農業を軸とする大地との対話を通して、このような音の世界を感じていました。
アメリカの作曲家であるアルヴィン・ルシエは、音によって空間が持っている性質を知ろうとしました。例えば、この空間では空調の音がずっと鳴っていますが、空調の音を消して、電気も消して、全く何も動いていない状態でも、この空間には微かな音が鳴っています。この空間自体が持っている共鳴周波数音です。例えば、大きな太い筒を耳に当てると、ボーッという低い音が聴こえます。小さい筒であればポーッという高い音が聴こえます。ビール瓶を耳に当てても、そのような音を聴くことができます。空間には、その空間が持っている響きが必ずあるのです。
それをちゃんと聴いてみようというプロジェクトが、ルシエによる「I am Sit-ting in a Room」です。タイトルでもあるこのフレーズを彼自身が朗読して録音した音を、スピーカーで再生し、その再生した音をもう一度録音します。それを何度も繰り返していくうちに、すでに2回目くらいではっきりとわかるのですが、その空間の持っている響きのようなものが感じられます。2回目から3回目にかけての段階で、風呂の中で喋っているような感じになっています。その空間自体が持つ反響音をキャッチして、最後には反響音ばかりの音になり、特定のピッチの音だけが強調されて、全く変わってしまうのです。
アメリカのアーティストのビル・フォンタナが、オーストラリアのアボリジニの村で実施した、音によって時間を測るプロジェクトについて紹介しましょう。海の上に架かる桟橋に、下まで貫通している丸い穴が8つ開いており、フォンタナは8つのマイクロフォンをそれぞれの穴に入れて録音しました。
海には満潮干潮があり、海面が下がったり上がったりする動きに合わせて、桟橋の下のスペースが広くなったり狭くなったりする。満潮になるにつれてピッチが高くなり、「チャッポンチャッポンチャッポンという音になる。干潮になってピッチが低くなると「ジャッポンジャッポンジャッポン」と音が下がっていく。その音を72時間ずっと録音するプロジェクトです。聴いてみると、満潮と干潮の間で時間が動いていることがわかるのですが、10分くらい聴くだけでは全くわかりません。満潮と干潮は1日に2回あって、6時間とか12時間くらい経つとピッチが変わっているのがわかるのです。
この作品はオーストラリアのギャラリーで展示されましたが、天井に設置された8つのスピーカーから、リアルタイムで現地から送られてきた音が降りてくるというインスタレーション作品でした。まさに音によって時間を測るというアプローチですね。
上述した例は、外部にある空間や時間を音によって測っていると考えることができますが、心理的なものを測ることについてもお話ししましょう。清少納言が書いた『枕草子』の中に、「ものへだてて聞くに」という特徴的な記述が何度も出てきます。清少納言はかなりの引っ込み思案で、あまり前に出てこない。物を隔てて色々なものを聴くことで、自分とそのものとの関係や、物理的あるいは社会的な距離を測ろうとしていました。
国文学者の石田譲二は、清少納言のこのような書き方は非肉体的であると論じましたが、私はそれとは真逆の考えでして、ここにこそ清少納言という人間の肉体的な特性が現れていると思います。耳は肉体の一部ですから、何かを隔てて聴くということに、清少納言の身体性が現れている。例えば、当時は通い婚だったので、男の人がやってきて指でポツポツポツと叩く。中で聴こえてはいるのですが、あえて意地悪をして反応しない。少しだけ衣の音をシュッシュッシュと立てて、向こうに気づいてもらおうとする。そんなふうに、ものを隔てながらやりとりすることで、音を通して心理的なものを測ろうとしていたのではないでしょうか。
これらの例の他にも、もっと色々なものが音によって測れるのではないかと思います。これから皆さんはフィールドワークを通して様々な音を聴きます。空間を聴くかもしれない。時間を聴くかもしれない。心理的な音を聴くかもしれない。密林で鳥や虫の鳴き声がたくさん聴こえるように、自分と対象との関係性を音として感じるかもしれません。けれども、「聴く」ということは、聴いていない音があるということでもあります。今、皆さんは私の声に注目していますが、向こうで子どもが喋っている声は聴いていません。私の大きな声が皆さんを支配しているから、他の声が聴こえてこないのです。あえて私の声を避けて向こうの声を聴くことも可能です。どのような声や音を聴いていないのかが、すごく大切なのです。聴いていない世界は、ものすごく広いのですから。
20世紀を代表する作曲家の武満徹の代表的な作品に、「音、沈黙と測りあえるほどに」があります。沈黙がこの世界を覆っていて、サイレンスの世界の聴こえない音「unheard sounds」の中で、どんな音の捉え方ができるのかが、この作品のポイントだと彼は言いたかったのでしょう。聴こえている音って世界のほんのひとかけらでしかなく、その周りには聴いていない音がたくさんあるのです。
中川先生の生き生きと時空を飛び超えるレクチャーの躍動感で、心が自由に解き放たれた。特に興味深かったのは、サイレンスの世界の聴いていない音。そんなことは考えたこともなかった。サウンドスケープについて自分なりに調べてはいたものの、私の見解をはるかに上回る壮大な内容に、音への意識や感覚、感情が大きく変化した。聴こえてこない音、聴こえていてもあえて拾わない音。ひとかけらの音の向こうにあるサイレンスに投影される自分という大宇宙を垣間見た知的なショック。さらに印象的だったのは、「サウンドスケープとは何か」という問いに対して、「わずか20分で説明できる」と前置きしながら、あえてその答えを明言しなかった中川先生の聡明な示唆。これを素直に受けとめ、自分なりの「聴くとは何か」を見出したい。(かとうあつこ)
「聴」という字は、神の声など、果てしなく遠い場所の音に耳を澄ますことを意味していたとのことだが、日を追うごとにこの話が味わい深くなってきた。そもそも聞こえるか聞こえないかの微妙な音を「聴く」とはどういうことなのか。「聴く」ということは、ある程度は能動的な行為なので、「聴こえるだろう」という予測や、「聴いたことがある」という経験がなければ成立しないように思う。かつての人々は「神の声を聴くことができる」「遥か遠くの、あるかないかわからないような音が存在する」という確信があったのか、何もないところから音を見出していたのか。存在しているけれど「聴いていない」音に気づくということをもう一歩越えて、「ないかもしれない」音を「聴く」という、確信も予測もなく、想像もできない音に真摯に耳を傾ける行為をしていこうと思う。(馬淵悠美)
LECTURE OUTLINE
中川真
2021年7月18日(日) 13:00–14:30
サウンドアートやサウンドスケープ、コミュニティアートなど幅広い分野で、ユニークな研究活動を続けている音楽学者の中川真さんを迎え、「聴く」ことの意味や、サウンドスケープの考え方についてお話をしていただきました。
1951年奈良県生まれ、京都府在住。1981年に十津川の盆踊りに触れて以来、その素晴らしさに魅了される。「盆踊りの活性化によるコミュニティの再構築」(京都市)、「文化とコミュニティ維持のための村落・都市共創システムの構築」(サントリー文化財団)のプロジェクトのコーディネートを行う。