REPORTS
- レクチャー
会田大也「ミュージアムエデュケーション的体験のデザイン」
2020年9月5日(土) 14:00–16:00
奈良県立大学 CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
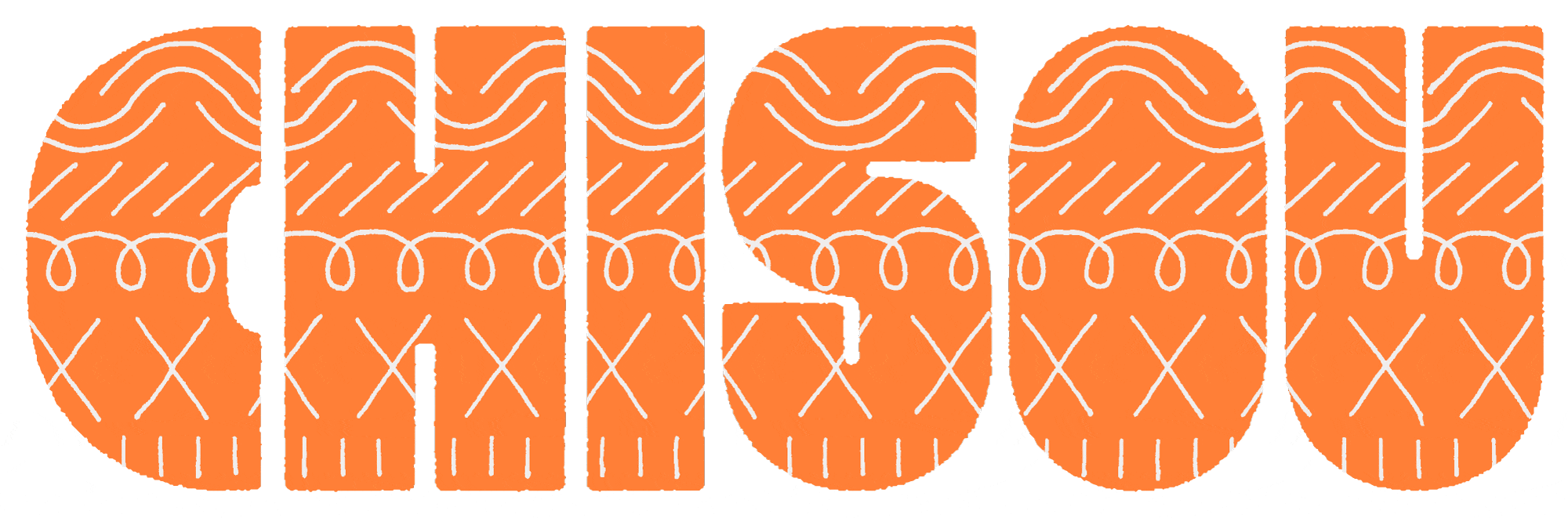
REPORTS
2020年9月5日(土) 14:00–16:00
奈良県立大学 CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

表現編の講師としてお招きした会田大也さんは、鑑賞者の主体性を引きだすプログラムやワークショップをアートセンターや美術館、芸術祭など様々な場所で実施してきました。会田さんによる二日間にわたるレクチャーとワークショップを開催し、アートを通じた豊かな学びの方法について考えました。

アートマネジメントは自分が主役というより、アートを楽しむ人々に良い体験をしてもらうという前提がある。さらにアーティストに良い活動をしてもらう、その周辺を整えていく仕事です。そして、アートを楽しむ人々の体験の質を担保するためには、ある程度のデザインが必要です。お客さんはどのように振るまうのか、アートとお客さんが触れ合うということはどういうことなのか、分解しながら考えていきましょう。
まず、アートは実際の社会とどう結びついているのかについて考えてみたいと思います。例えば、企業の社長がアーティストにお金を提供して作品をつくる時、また行政組織がアートフェスティバルに税金を投入する時、納税者など他者に対して説明が必要になり、「アートは何かに役立つのか」という話が議論になると思います。
アーティストの立場からすると、社会に役立てようと考えて作品をつくっているのではなく、もともとの動機は「これはアートである」という理由によってのみ成立しているのが作品です。どこかの要請に応えるのではなく、アートはアートとして自律している、ということは忘れない方が良いでしょう。ただし、作家の意図だけが尊重されるわけではなく、周りの人が作品をうまく活かして観光資源として社会に役立てている場合もある。しかし、アーティスト本人は観光資源になるためにつくっているわけではない。これは前提として確認しておきたいと思います。
二〇一九年十一月に十八歳を対象に意識調査した「18歳意識調査」が行われました。日本、インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ドイツ、各国千人ずつ調査しており、その設問の中に「あなた自身についてお答えください」という項目があります。例えば、「自分を大人だと思う」という項目では、日本が一番低くて29.1%の人が大人だと思っている。中国だと89.9%が自分は大人だと認識している。ことさら低いのが「自分で国や社会を変えられると思う」という項目です。YESと答えた人は日本で18.3%。一番高いインドだと84.3%。この差は歴然ですね。なぜ、日本の十八歳の若者たちは、自分で国や社会を変えられると思わないんだろうかと、すごく気になっています。そういう環境や自由が与えられていないということがあるのかなと。「おかしいぞ」と思うことがあった時に「これが現状だし……自分で変えられるわけないし……」と思ってしまうと、それ以上思考は深まらない。
これに関連して、二〇〇一年、二〇〇七年、二〇一三年に高校生の規範意識を連続して調べた調査があります。その中に「校則を守るのは当然です」という質問があり、それについて「そう思う」と肯定している人の割合が一気に伸びているのに対して、「どちらかといえばそう思う」という人の割合はあまり変わらない。「どちらかといえばそう思わない」と答えた人は減ってきている。これらの意識と「国や社会は変えられない」と思ってしまう背景には共通点があるのではと感じています。
山口情報芸術センター[YCAM]のプログラムを紹介したいと思います。通常、展示室にはアーティストの思考の結果としての作品が置かれています。そこには「思考の軌跡の形跡しか残っていない」という言い方もできるのではないでしょうか。「形跡としての作品だけでなく、試行錯誤のダイナミズムそのものを見せることはできないか」という問題意識から、ものを見る場所に公園をつくり、その中で遊びをどんどん生みだす。その環境そのものを作品として見せる取り組みを行いました。

二〇一二年にギャラリーの中に「コロガル公園」をつくり、二〇一三年に屋外に「コロガルパビリオン」を仮設建築としてつくり、その中を遊び場にしました。二〇一六年に「コロガルガーデン」、二〇一八年「コロガル公園コモンズ」へと展開していきました。「コロガルパビリオン」では、公園内にメディアを使った仕掛けが埋め込まれていて、光ったり、音声がずれて流れたり、エコーがかかったり、ボイスチェンジャーで声が変わったりする装置がありました。すぐそばに自然環境があるため、雨が降ったり水溜りができたり、穴が空いたり、そういった現象も遊びの一つの要素になっています。アナログなものとデジタルなものを分けるのは、子どもにとっては意味がなく、それらが一緒くたになっていくことに可能性を感じます。
「コロガル公園」には「こんな公園あったらいいなシート」があり、自分が思い描く公園のアイデアをポストに投稿できます。集まったアイデアをネタにして、子どもが参加する「子どもあそび場ミーティング」を行いました。YCAMにはものづくりチーム「インターラボ」があり、その人たちとディスカッションしながらアイデアを実現していきます。ミーティング期間中は公園の活動を止めて、大人たちも本気で関わり、できあがったアイデアを実装していく。子どもたちにとって、考えたことが実現することを実感できるプログラムです。
このプログラムのルーツには、デンマークのランドスケープデザイナーであり建築家のカール・テオドール・ソーレンセンの考えがあります。ソーレンセンは、自分で設計した公園が完成した時、公園の後ろにあった資材置き場に子どもが集まっていた光景を見て、綺麗なものをデザインしてもだめで、野性味の溢れる、自分たちが自由に変えることができる空間こそ、子どもが求めているんだと気がつき、その可能性を追究しました。
重要なのは、作品そのものよりも、作品を見て議論してお客さん自身が何かをつくりだしていく、そのプロセスだと思っています。例えば、「遊ぶ」ことは無限のエネルギーの源です。「遊ぶ」ことに関しては皆が欲望するので、そこからエネルギーが生まれ続けている。
小さな頃の遊びを思い出すとわかりますが、実は「遊ぶ」ことは全く論理的ではないですよね。例えば、野球を初めてする時、ルールがわからない。打った後でサードに走っちゃうみたいな。でも次の瞬間にはサードに走ってもいいことになったりして、その場でルールが組み替えられる。組み替えられて数分後には、それが禁止事項になっていたり……とにかくその場に対する破綻と引用と、それに対する抵抗のようなものがずっと拮抗している。それが遊びの面白くて非常にスリリングなところです。
立場がどんどん入れ替わりながら一体化がどんどん起きていく。前述の「子どもあそび場ミーティング」では参加する大人たちの振るまいを見ていると、何かを指導する立場ではなく、子どもたちと一緒に考えている。四人くらいのグループで一体感をもって絡み合いながらアイデアを出し、誰が言ったかわからないアイデアでも、自分が言った気になっているわけですね。そのような一体感みたいなものが生じて、最終的なアイデアのオーナーシップみたいなものが生まれていく。そのためには客や講師という立場ではなく、固定しない立場の入れ替わりを、かれらは無意識的に行っていた。参加者が自分の脳みそで考える技術を鍛えていくことが、非常に重要なのではないか。さらに、これがアートの現場で起きるということが、重要なのではないかと僕は考えています。
アートの見方がわからないとか、難しいなと思う人が社会全体では多数派かもしれません。その背景には、作品を見るということが「作家の意図を当てる」というある種のゲームと結びついていることが強くあるのではと思います。「わからない」ということは「作家の意図が何なのかがわからない」ということを意味しているのではないでしょうか。いろいろなアーティストと話をすると「作家の意図を当ててもらえて嬉しい」という人はあまりいなくて、「僕はこういうふうにつくったけれど、全く違う見方をする人がいたら面白い」というような、違う読み解きをしてくれる人を歓迎しています。
「約十秒」という数字についてご紹介したいと思います。美術館で実際に一枚の絵画を見る時間が十秒との調査結果があります。人はあまりじっくり見ないということですね。一九二八年にアメリカで行われた調査で、大きなミュージアムから小さなギャラリーまで、入館から退館まで何分何秒かという時間数を、展示作品の点数で割り算して、一点あたり何秒かというのを単純に計算した数字です。では、日本はどうなのか。ほぼ同じ方法で八〇年代に調査が行われましたが、藤田嗣治は二十六秒。日展だと膨大な作品数なので七・四秒で、一点あたりは短くなっていく。
八〇年代から九〇年代にかけてニューヨークのMoMA が実施した調査では、知識を提供するタイプのガイドツアーだと、参加者はほとんど覚えていないということがわかり、対話型鑑賞やヴィジュアルシンキング型カリキュラムが開発されました。作品を見てお客さんが発する言葉から作品鑑賞を進めていくという方法です。

鑑賞者の中で何が起きているのかについて分解して考えていくと、まず第一印象として好きとか嫌いとか、気持ち悪いとか怖いとかを感じます。次に、どんな要素が作品にあるのかを認識していく。例えば「この作品に何が描かれていますか」と質問されると、「欄干のようなものが見えます」となる。欄干が見えるとしたら、そこはバルコニーなのかな……とイメージがどんどんつながっていく。要素同士がつながり、ストーリーや背景を想像すると、意味が立ち上がってくる。すると、この絵は自分にとってどんな意味をもつのかと考える。すると他人が見た時にどうイメージするのかというのが見えてくる。しかし、作品を十秒以内で見るとなると、第一印象で止まってしまう。他者と喋りながらしっかり見ていくことによって、第一印象を裏切られることが起きるのですが、この時の快楽みたいなものがアートを見る喜びとつながっているのではないかと思います。
鑑賞とは、視覚的のみならず言語的な活動だということもポイントです。作品を前にして、他人と対話しながら鑑賞することは、豊かな鑑賞体験につながります。もちろん自分一人で見るのも良いですが、自分以外の人と一緒に見て対話することで豊かな鑑賞体験になり得る。専門家による評論に書かれた「正しい」知識や解釈だけが作品の見方ではなく、そもそも専門家の評価も時代によって変わっていくことを、皆さんのようなアートマネジメントに関わる方々には知っておいていただけると嬉しいです。
今日、皆さんが実際に行うのは、マーケティング分野で使われる「カスタマージャーニーマップ」という手法です。顧客の一連の行動を「旅」に見立てて一覧にすることで、経験や思考を分析する可視化手法の一つです。例えば「アートが好き」、「アートが苦手」というようにざっくりと顧客を理解するのではなく、シーンごとにどんなことを考えているのか、詳細に分析することで課題を絞り込めるメリットがあります。僕はミュージアムエデュケーターという立場のため、来場者が入り口のドアから入って、会場を巡り、出口から出ていくところまで、一連の体験を思い描きます。展覧会が一番スタンダードな考え方ですが、必ずしも展覧会企画でなくても良い。アートプロジェクトや長期的な取り組みを行う可能性もある。それに対して来場者がどのように心象風景を描いていくかということを、シーンごとにリアルに想像して全部書きだしてみましょう。
① グループをA〜Cまで三つに分ける
② Aは「事前決定(行こう!)」「会場周辺(着いたぞ)」「帰路」の各シーンを書きだす
Bは「事前に調べる(どんな感じ?)」「体験の中心地」「その日の夜」の各シーンを書きだす
Cは「往路」「直後、帰り際」「元の生活」の各シーンを書きだす
③ それぞれのシーンと行動を一覧表にまとめて、全グループで共有し、シーンごとに見ていく

事前に調べるというのはどういうことでしょうか。「まずどこでやっているか」、「何がやっているか」、「道中においしいご飯屋さんがあるか」。これが三つ目にあるのは面白いですね。確かにご飯とセットで考えますよね。
往路ではどんなことを考えているでしょうか。「美味しいご飯屋さん」。やっぱりご飯屋さんは大事ですね。「見きれないんじゃないかな」とかリアルですね。「建築家は誰だろう」。これ結構面白いですね。例えば特別展だけでなく常設展は何がやっているかなと調べていったり、道すがら考えたりしますよね。ついでに何を見るか、みたいなことを考えますよね。そういうのも結構重要です。そう考えると美術館の役割は観光産業とも結びつきます。
「屋内展示でも野外展示でも看板が出ていないと不安になる」。そう、順路がわからないことがありますね。「案内スタッフの手が空いてそうな時間に行こうかな」。案内スタッフの方とおしゃべりするっていうのが目的になっている場合もあるということですね。
「壁と床の色が気になる」。特に僕はメディアアートの分野にいるので、建物を見ると、ここは不利だなと思ったりしますね。会場構成や動線が気になったりもします。「映像作品が多いのは輸送費がなかったからとか?」。実際、映像作品が多くなってきているのは、アーティストがシリアスに考えるものがやはり映像でしか表せないというのがあるかもしれないですね。「作品の間隔、人の集まり方」。これはコロナ以前から考えていたことですが、コロナ禍においても隣の作品が邪魔でよく鑑賞できないということもあるかもしれないですね。
「メインの作品も良かったけど他の作品も良かったなぁ、時間に余裕をもたせたら良かった」。最後駆け足になるっていうのもよくありますね。「お茶飲みたい」。館内にベンチを置く場所は、ミュージアムエデュケーションの立場からアドバイスをすることもありますね。
「展示を見た後に誰に共有しようかを考える」、「頭フル回転でどう言語化しようかなと考える」、「友達や家族と共有したいなとか」。やはり自分が得た体験を他者に共有したり、議論したりしながら、展開させていくというようなことを考えるということですね。
「友達や家族に文句や愚痴を言う、面白くなかったことについて」。こういうのも結構重要ですね。自分の中に留めるのではなく、誰かに言うということですね。「しんどいテーマの作品は出た瞬間に一回忘れるが、後で思い出してみる」。確かに作品というのは必ずしもポジティブなものだけではないので、すぐに向き合うのはしんどいと思っても、後からあれはなんだったのだろうなと思い返すというのはありますね。「他の人がどう批評しているか記事を読む」。二十年前だと、他の人とどうシェアするかということではなく、自分の内側での経験として留めていたことが、現代においては他の人とどう交換できるかということに変化していますね。
では、元の生活に戻ってどういうことをするか。「スマホのカメラで写真を撮るとき構図にこだわる」、「普段使う食器を凝ってみる」、「いつもの通勤コースで違う道を通ってみようかな」。日常の中に違和感を差し込んでくるというのがアートの一番面白いところだなと思うので、アートがきっかけでそういった変化や、オルタナティブを探してみようという気づきが、普段の行動に反映していくというのは面白いです。

非常に豊かなシーンが出てきました。これらはディテールですが、このようなディテールがあることこそ来場者の振るまいだと思います。自分で企画を考える時は、このような細かなことを想像しないで考えてしまいがちです。チームで動く場合はチーム全体でこのマップを共有することが、後々の企画を立てていく時に気遣う物事の細かさに影響してきます。アートマネジメントは、アートプロジェクトやコンテンツを計画して実行する場を整えていく仕事ですので、そのような時に来場者の体験をこういった非常に細かな解像度で捉えていくこと、マネジメントに関わる人たちで、この解像度を共有することから議論を始めるのはとても重要です。そのために、このような「来場者の気持ち」を可視化する取り組みから始めるのも一つかなと思います。
私はこれまで地域型アートプロジェクトの現場で、アーティストの意向や目的が、行政やマネージャーに十分理解されず、食い違いが起きるという事例を少なからず目の当たりにしてきた。しかし今回のレクチャーで、その原因はそれぞれの立場によって言語や表現が大きく違っていることだと気づいた。つまり最も重要なロジスティックスの一つは、行政、マネジメント、そしてアーティストの間に共通言語をつくることだと考える。また相互理解を円滑に促すために、マネージャーとアーティストの間でより密なコミュニケーションをとり、十分なエビデンスを集めた上で、行政に対して論理的にわかりやすく伝えることも必要である。そのためにアートという枠組みを超え、他分野の学者や学生の研究を用いることも一つの手立てとして有効ではないだろうか。(和田真依)
「なんとなく」ではなく、「リアル」に想像すること。そのためには、時間と空間の流れに⾝を置いて、じっくりと向き合い、「味わう」ことが大切。⽇常において、時間と空間の流れの渦に巻き込まれ、五感を開放して味わう楽しさを置いてきてしまっていることに気づいた。「なんとなく好き」や「なんとなく気になる」を⼀つひとつ拾い上げ、「好き」や「気になる」ポイントに向き合うことで、リアルと出会い、リアルを超えた場所へと旅に出ることができるように思う。(鈴木結加里)
「言葉で詰めていけばいくほど、言葉にならないものが見えてくる」と、会田さんがおっしゃっていたのが印象的だった。アート作品を鑑賞し、それについて述べる時、どうしても抽象的な言葉で感覚的に表現してしまう自分がいた。芸術は感性でみるものだから、言葉では表現しきれないと思い込んでいた節もある。決して間違いではないが、そう言い切ってしまうのも一つの思い込みだったと感じた。人間は、言葉によって解し合い発展してきた。既に言葉という道具を持ってしまった以上、それがない世界に戻ることは困難である。言葉にならない領域を知るために、言葉を使い尽くすことは一つの糸口になると感じた。(早田典央)
売れ始めたアーティストは社会の役に立つものとしてアートを語りがちで、ピュアなアーティストはそうではないとか、でも周りがそれを活用することで、あるいは観ることで結果として役に立っている、といった会田さんの整理は的を得ている。それでも会田さんは、「これはアートである」という理由のみに拠って立つものこそがやはりアートだというのが個人的な見解だという。
ただ、頭で考えるコンセプチュアルなアーティストだったり、ある意味で成熟したアーティストは、作品とは別に言葉もまた饒舌になる。その場合、かれらが生み出すものはアートではないのか。僕の現時点での整理としては、アートを「文系の知」と捉えることだ。つまり、アートは、50年後や100年後に役に立つものである、と。そう考えれば、僕からすれば会田さんもアーティストだし、コロガル公園はアートだと思う。
レクチャーでは、会田さんが対象にする子どもたちとピュアなアーティストが、遊びと作品制作が、それぞれ対応的に語られていたように感じた。そこでは共に、矛盾や破綻、飛躍が重要な要素となる。ただ、遊ぶことは誰にでもできる。会田さんが示したそのシンプルな手法が、言葉を使って他人の視点を共有するというものだった。西山さんのレクチャーと対比的に言えば、歴史だけでなく、横にいる人もまた壮大であるということを実感した。