REPORTS
- レクチャー
三浦雅之&ラナシンハ・ニルマラ「農による自給的生活文化の継承と創造」
2020年10月28日(水) 14:00–16:00
清澄の里 粟
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
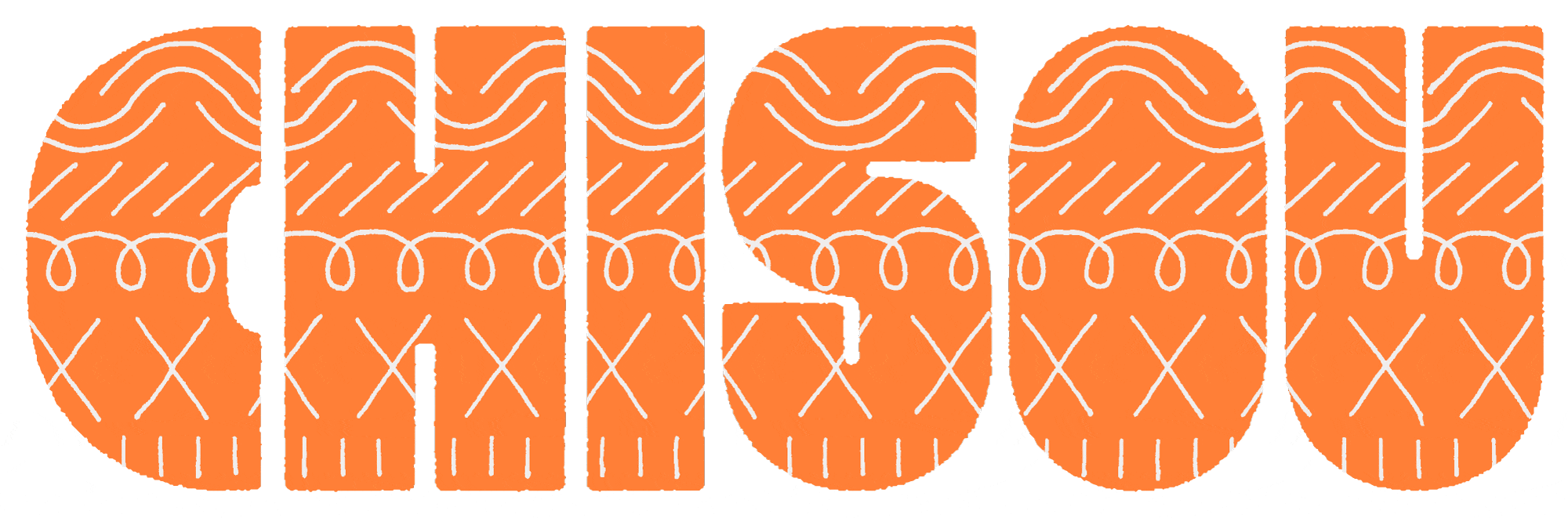
REPORTS
2020年10月28日(水) 14:00–16:00
清澄の里 粟
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

奈良の中山間地である清澄の里で、在来作物の調査研究・栽培保存に取り組む農業家の三浦雅之さんに、地域に根ざした活動「プロジェクト粟」を介して世代とコミュニティをつなぐ自給的生活文化の継承と創造についてお話いただきました。コメンテーターとしてお招きしたのは、スリランカの在来資源の価値を掘り起こす取り組みについてフィールドワークをしている観光社会学者のラナシンハ・ニルマラさん。三浦さんご夫妻が営むレストラン「清澄の里 粟」でお二人によるお話を聞いた後、周辺を歩いて自然環境や畑を見学しました。
CONTENTS

まず初めに、芸術の「藝」の語源についてお話したいと思います。亀の甲羅に刻まれた文字「甲骨文」と、青銅器の中に書かれていた文字「金文」がそもそもの起源ですが、実は農業を意味しており、女性が木を植えている姿から文字が生まれました。漢字研究家として有名な白川静さんの『字統』にも書かれています。今日、ここで私が農業のお話をするのは、ある意味で必然なのではと感じています。
お店の屋号もプロジェクト名も「粟」ですが、大切な意味が込められています。大和言葉の研究者、林英臣さんの著書によると、大和言葉では「あ」にはすべての始まりという意味があり、「わ」にはすべての調和という意味がある。聖徳太子の「和を以って貴しと為す」という言葉もそうですが、和を大事にしようとか、友達の和をとりもつというように、今でも調和のイメージで使われますよね。
粟には、いろいろ縁起の良い意味が込められていて、旧暦の中にある「一粒万倍日」という事始めの吉日は、粟から生まれた言葉です。一粒のお米の種を蒔くと、どれくらいに増えるかご存知ですか。様々な品種がありますが、私たちが普段食べているヒノヒカリやコシヒカリなどは二千粒くらいに増えるものが多く、たくさん採れる品種だと四千粒くらい。ところが粟は、一粒蒔くと一万粒くらい増える。豊穣を最も象徴している穀物なのです。
伝統野菜の種を守り広げていく、その過程で地域を活性化していくという目標をもって「プロジェクト粟」は生まれました。本日皆さんにお越しいただいている、奈良市高樋町を中心とした精華地区(旧五ヶ谷村)、別名が清澄の里と呼ばれるエリアが、そのフィールドです。人口は約千人、家の数は約三百軒で、典型的な村です。奈良の市街地にも近く、ここの標高が百三十メートル、そして車で五分ほど走ると四百メートルのところもあり、平地から高原までいろいろな気候をもっている中山間地域です。
我々が考えた事業スキームは三角形でして、「プロジェクト粟」では三つの組織を運営しています。まず、様々な伝統野菜の調査研究や在来ヤギの保存活動など、公益の活動を行うNPO法人清澄の村。地域の各世代の中心人物が役員として加わってくださっています。この二十年間で奈良県全域を回り、地域に眠っている在来作物や伝統野菜を調査し、どのように活用され受け継がれてきたのかを調べてきました。種をお預かりし保存するシードバンク事業も行っております。
次に、この中山間地域を活性していくために地元の集落営農を行う組織「五ヶ谷営農協議会」をつくりました。様々な遊休農地の対策を行ったり、伝統野菜を実際に計画栽培したりして、それを三つ目の組織である株式会社「粟」の飲食事業や加工品事業ですべて買いとり、レストランの食材として用いたり、商品開発を行ったりします。
これら三つの組織で、伝統野菜の種の調査と保存、栽培、活用という三つを連携して行う「六次化」が、「プロジェクト粟」のスキームです。伝統野菜を守り継承していくことは、お金にならなくてもやらなければなりませんが、実際に自然な形で継続していくためには、生産して活用され、皆さんが喜ぶから皆がつくりたくなり、またつくっていくというサイクルを生むことが一番です。そのための仕組みを考えた末に、これら三つの組織を立ち上げるに至りました。

今皆さんがいらっしゃる農家レストラン「清澄の里 粟」ですが、二十一年前は農家レストランという言葉さえありませんでした。今では、全国各地で地域活性の手法や、農家が付加価値をつけて営みを継続していくための方法論として、非常に注目されています。ヤギが暮らすなか、この里でつくられた伝統野菜が中心のお料理を提供しています。一つのコースで五十種類以上の食材をお召し上がりいただけます。年間百五十種類ほどの野菜を栽培していますが、皆さん馴染みのないものばかりですので、できるだけ五感で感じて食べていただきたいと思っています。
また、特産の五ヶ谷生姜を使ったソフトクリームなど地域資源を活用した新商品開発も大学と連携して行っています。奈良には六種類の粟があり、その中でも最高級といわれる「むこだまし」。ほぼ絶滅していたのですが、たまたま種を持っていらっしゃったおばあさんと出会い、今では約三百坪の畑で生産しています。この「むこだまし」を加工して「粟生」という和菓子をつくっています。平城京遷都千三百年の時に、皇太子だった今の天皇陛下が春日大社を御参拝されたのですが、そこで提供する和菓子として「粟生」を選んでいただきました。私たちは地元で生産することにこだわっていますので、大量に粟を生産できない。お土産にすればたくさん売れますが、今は店で提供させていただくにとどまっています。
他にも様々な食育の活動を行っています。いろいろな野菜の絵が店内に飾られていますが、天理市に暮らしている作家さんが、私たちがつくった野菜を十六年間描き続けてくれています。その絵を使ったカルタを食育の教材としてつくりました。今までずっと伝統野菜を守りつなぐ活動をしてきましたが、さらにそれを広げていくような取り組みにも力を入れています。
「プロジェクト粟」では、近畿大学と十年以上連携して、生物多様性を保全する取り組みを続けています。例えば、レッドデータに載っている世界最小のネズミ、ニホンカヤネズミのような希少な生き物が生息する豊かな自然環境が奈良にはまだまだあります。それを守っていくために、生物多様性も視野に入れた農業の取り組みを行っています。
その一つが、絶滅したペタキンと呼ばれるニッポンパラタナゴを復活させるプロジェクトで、この店の裏でペタキンの繁殖に取り組んでいます。この魚が生息できる環境は、非常に健康的な生態系であることを表しています。伝統野菜だけでなく生物多様性も守っていくために、この水を使った農作物を新しく商品開発し、行政のお金に頼らず自走していける仕組みをつくっていこうとしています。
これからヤギの話をしようと思っていると、ちょうどペーター君とハナちゃんが来ましたね。脚が短い「シバヤギ」という在来種のヤギでして、近年は減少しています。ちょうど二十年前に飼育を始めて、これまで三十九回の出産を経て、七十九頭が生まれました。いろいろな方々にヤギをもらっていただき、ネットワークができていくような形で、在来種のヤギの保存をしています。かれらは可愛い上に、お店の仕事を三つほどしてくれます。雑草を一緒に刈ってくれたり、野菜くずを食べて土に返してくれたり、接客もしてくれる、欠かせない存在です。ちなみにペータ君はカメラ目線とポージングが完璧ですので、一緒にお写真を撮りたい方がいらっしゃればぜひ。

もう一つの取り組みとして、奈良で眠っている歴史的、文化的資源を掘り起こしてアーカイブ化したり共有したり、もしくは行政関係者やメディア、クリエイター、研究者、事業者、農家が協働して活用したりすることにより地方創生をしようという目的で、「はじまりの奈良フォーラム」を月に一回開催しています。奈良発祥のものがいっぱいありまして、例えば御所柿は日本初の完全甘柿ですが、日本一の柿博士である浜崎貞弘さんに講義していただいたりして、月刊誌『ディスカバー・ジャパン』で記事にまとめてアーカイブ化しています。

妻の陽子と『家族野菜を未来につなぐ』( 学術出版社、二〇一三年)を著した翌年、国連は国際家族農業年を定めました。当時、日本では大規模化と付加価値化という二本柱で農業政策が進められていたので、小さな農業に注目する風潮ではなく、国際家族農業年は普及しませんでした。世界では人口が増えすぎて農業が限界にきています。食糧不足を打破していくために、多収の作物をつくる品種改良や生産技術の向上に加えて、家庭菜園やプランター菜園、屋上菜園などで皆が少しずつ食べ物をつくるということが重要です。このような小さな農業を見直そうというのが国際家族農業年です。その中で在来作物が大きな役割を果たすと私は思っています。
例えば、うちの村には親子三世代で「椿尾ごんぼ」という伝統的なゴボウをつくっているご家族がいます。売るためではなく、自分たちが食べたり、お歳暮としてお世話になった方々に配ったりしている。誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら生産を続けてこられました。私は調査に行った時に必ず二つの質問をしますが、一つはなぜつくってこられたのか、もう一つはどうしてつくっているのかということ。多くの方々が当たり前という顔で「つくりやすいから」とおっしゃいます。もう一つについても、当たり前という顔で皆さんこう言うんです。「美味しいから」とか、お孫さんを思い浮かべて「誰々が好きやから」と。そんな言葉にたくさん出会うものですから、これは伝統野菜や在来作物をつくっていく時の一つのエッセンスなのだと気づかされました。
「つくりやすい」ということは気候風土に適応しているということ。「喜ぶ顔が見たいから」というのは、個人の嗜好性を大事にしているということです。今、食の安心安全が叫ばれているなかで、これほど大切な言葉があるでしょうか。食べる人の顔まで思い浮かべて野菜をつくる農家は少ないと思います。農業の変遷の中で、大きな農業だけでなく、小さな農業も組み合わせて、人類の課題に取り組んでいかなければなりませんが、伝統野菜をつくってこられた方々のこのエッセンスが、これからのキーワードになっていくのではないでしょうか。
伝統野菜は、現代の民藝ではないかと考えています。柳宗悦が提唱した民藝は、もともと日本がもっていた手仕事や生活文化の素晴らしさと技を表現する心でしたが、いつしか民藝運動は物が対象になり金持ちの贅沢品になってしまった。民藝研究者の鞍田崇さんとお会いした時、伝統野菜がその役割を果たす可能性があるという話になりました。伝統野菜は、それ以外の野菜と比べて、「七つの風」に非常にリンクしているからです。「七つの風」というコンセプトは、地域に眠る新しい知を見つけだす一つのまなざしになるものです。
一つ目の風は、その地域特有の「風土」です。標高や風の流れ、降水量など、その地域がもつ最もベーシックな性質である風土を活かして、人間は生きていくために農作物をつくります。この「風味」が二つ目の風。農作物や酒、果物、山の幸などがあります。霜が降りると白菜が甘くなると言われますが、同じ品種でもその地域特有の気候だからこそ生まれる風味があります。

風土の中で風味をつくっていくなかで生まれるのが、三つ目の「風景」です。例えば、棚田は自然の原風景ではなく、人間の営みと自然のコラボレーションから生まれた美しい風景です。奈良だとどこにでも柿がありますが、いつかどこかで誰かが柿を植えているからこそです。四つ目の風は「風習」。生きるための知恵を指しており、食文化や伝統芸能も含まれます。日本には四季があり、細かく分けると二十四節気になる。昔の人たちは五日ごとに自然の変化を感じていたので、さらに七十二候に分けられる。昔は皆が当たり前のように用いていた生活の知恵でしたが、しっかり見つめ直すことが、これから大切になっていくのではと思います。
五つ目の風は「風物」、つまり生活工芸のことです。人間国宝がつくる美術工芸もありますが、特に大切にしたいのは生活工芸です。江戸時代では九十九%以上の物が自然から生まれていましたが、現代はプラスチックや石油製品が大きな問題になっています。そもそも人間は自然の中で自然を活かして生きてきたので、そのような生業に再び目を向けていく必要があります。
六つ目は「風俗」で、生活文化を指しています。WHOが定めるワークライフバランスは八時間睡眠、八時間労働、八時間余暇ですが、それとは異なる世界がいろいろある。第二次世界大戦後、日本人研究をした海外の文化人類学者が、日本人は遊ぶこと、働くこと、学ぶことが渾然一体となった素晴らしい民族であると言いました。渡辺京二さんが『逝きし世の面影』(平凡社、二〇〇五年)でその時の言葉をまとめていますが、そもそも日本人は遊・学・働が融合した最高の生活文化をもっていたのです。
それら六つの風を感じるなかで生まれる日本人の心持ちや価値観、すなわち「風情」が最後の風です。例えば、営農協議会の会長は農作業で昔ながらの「はざ掛け」を続けていますが、これによって子どもや老人が手伝える関わりしろが生まれます。関わりしろがあることで、かれらが見聞きする景色や出来事まで食卓に隠し味として伝わっていくのではないか。そのようなものが伝統野菜の中に眠っているのではないかということをお伝えして、レクチャーを締めくくりたいと思います。
三浦さんのお話を聞きながら、スリランカのことをいろいろと思い浮かべていました。店に入ってすぐに気づいたのが、蛇のような形のヘビウリ。スリランカにもそっくりなセイロンウリがあります。奈良だと普通のスーパーでは売っていませんが、ファーマーズマーケットに行くと手に入る。スリランカでも伝統野菜のようなものを扱う小さなお店で買えます。現代はファーストフードで世界がつながっていますが、三浦さんがインドからその種を持ってきたとおっしゃっていたように、健康に良い伝統野菜で世界がつながるというのは本当に素晴らしいことだと感じます。
スリランカでも最近は伝統野菜がもつ健康面での意義が再認識されて、伝統野菜を扱うレストランもあります。例えば、スリランカの伝統的な米の種類は約三百以上ありますが、普段食べているのは三種類とか五種類くらいです。そういった多様な種類を再発見して、シードバンクみたいに種を保存していこうという動きも少しずつ見られます。スリランカの場合は、政府であれ非政府組織であれ、若い人がいろいろやりたいと思っても、ちゃんとしたリーダーシップがないということが大きな問題ですが、若い頃から三浦さんが実践してきたということは、すごく重要なことではないかと感じました。
人が生き残るために本当に大事なものとして、食べ物、水、綺麗な空気の三つがある。経済がどれほど発展しても、人が生き残るために必要なものは変わらないのに、それが無視されるような生活を世界中でしてきました。コロナ禍でスリランカでは厳しいロックダウンが課され、全く家を出られなくなり、お金があっても食べ物を確保するのが難しい時期が一ヶ月ほど続きました。そのような時にSNSでは家族菜園をしようという動きがありました。スリランカの人々はアパートやマンションではなく、小さな庭のある家で暮らしているので、都市に住んでいる人でも栽培できます。若者も栽培してSNSにアップしていました。スリランカではブームが起きても後で全くしなくなることがあるので、継続していくことが大事です。SDGsで謳う「飢餓をゼロに」という目標も、持続可能な農業と結びついています。どこの国であれ地域であれ、食料を他の国や地域に依存しないこと、自給自足を考えていくべきだということを、コロナ禍から学びました。そういった面においても三浦さんが実践されていることは非常に意味があると思いました。

新型コロナウイルス感染症のような病気に対抗するために、伝統野菜などの健康的な食を心がけて免疫力を高めることも大切です。食そのものが薬になるという考えは、スリランカでもある程度は定着してきています。健康面からのみならず、奈良の場合は観光ともつながっており、海外や他の地域からの観光客が、その土地の伝統的な野菜や食材を食べられることには、非常に大きな意味があります。また、野菜をメインとした食生活は、排気ガスや二酸化酸素をたくさん排出する肉を食べるよりも、自然環境に良いですね。
また、三浦さんがつくった、面白い形をした野菜の写真を集めた野菜アートの本を見ていると、野菜の形はこんなにいろいろあったのかと驚きます。私たちには「この野菜はこの形」という思い込みがあり、普通だったら形が違うのは良くないと思うのですが、それをアートとして捉えて発信していくのが良い。その背後には大きな可能性や意味があり、食品廃棄を減らす方向にもつながると思います。
三浦さんの七つの風のお話を聞いていると、自分でもできるかもしれないという感覚が芽生えてきます。小さな農業で自分が食べるものを自分でつくってみたいという気になってくる。日本では全くやってこなかった身としても、小さなことからできるかもと感じさせられました。三浦さんにお聞きしたいのですが、個々人がやりたいと思った時、まずどういうことから始めることができるのでしょう。アドバイスをいただけると嬉しいです。
プロの農家にならなくても、農的なものをちょっと取り入れようとするなら、様々なガイドブックもありますし、農学校もたくさんあります。遊休農地を解消するために貸し農園や体験農園をしている会社もありますので、こういうところで実際に自分でやってみるのが具体的な一つの手です。もしくは、いろいろなご縁で「うちの畑が空いている」という話も、特にこれからはいっぱい出てくると思いますね。
コロナ禍の中で、自分の健康は自分で管理しようという機運が高まっており、伝統野菜や発酵食品が見直されています。奈良は発酵食品の発祥地でもあり、柿の葉寿司や奈良漬、清酒など、たくさんの発酵食品があります。こういったものを自分の生活に取り入れていこうとする人たちも増えています。そして、「七つの風」にリンクした食、エネルギー、住家、学び、生業、健康、助け合いという「七つの自給率」を高めていくというトレンドが必ずやってくると思っています。この七つの自給率を高めていくと結果的に豊さと幸せの自給率も高まります。お金でサービスを買う代わりに誰かに委ねていたものを、自分たちの手に握り直すという動きです。
七つの中の自分が好きな分野から始めていくと、類は友を呼び、別の分野で自給している人と必ずつながるでしょう。自分が得意なもの、好きなもの、ワクワクするもの、小さなところから取っかかりを見つけていくことが、実は近道ではないでしょうか。それが水面に少しずつさざ波を立たせ、波になり、うねりになって、つながっていくのではないかと思っています。

伝統野菜による地域活性に取り組むプロジェクト粟の活動に
ついて伺った。その土地で人間が生活するための基盤として農業
があり、またその活動を通して共感が生まれ、健康的なコミュニ
ティが形成されていく。食や農を通して、人と人、人と地域をつ
なぐ技術は、まさに「生きる技術」としてのアートマネジメントだ
と感じた。(櫻井莉菜)
フィールドワークで、豆はあえて雑草を刈らずに種を蒔くことで鳥に啄まれないという話を聞き、ある本の一節を思い出した。「田んぼの外に雑に蒔いた雑草だらけの場所に生きる作物の方が立派だった。」自然の中であらゆる生物は、あるがままに生きている。それを知ろうとせず、合理性・利便性ばかり求め続けることは、この上なく愚かな行為だと感じた。(山本篤子)
小学生の頃に「本当に美味しい」と思った給食のメニューがある。黄ニラのお吸い物だ。子どもの頃は食材や料理に興味がなく特に気にしなかったが、成長するにつれて黄ニラが地元岡山県の特産品であり、市場にあまり出回らない希少な野菜であると知った。給食でそれをいただけるとは、なんて恵まれているのだろうと、岡山を誇らしく感じるようになった。奈良にも、地域で昔からつくられている「大和野菜」がある。土地の風土によく合って栽培しやすく、美味。値段は他の地域や外国産の方が安く、学生である私には手が届きにくい存在だが、地域の人々に美味しさと誇りを与えてくれる地場野菜は、これからも継承されていってほしいと願う。三浦さんはそのために大和野菜を美味しく調理して気軽に楽しめる場を設けたり、「大和の野菜いろはカルタ」を制作された事例を紹介されていたが、自分たちでもその方法を考えてみたい。(石川理香子)
三浦さんは三つの組織を運営し、それらを有機的につなげながら独自の事業を展開している。その事業スキームが美しい。NPO(調査研究)と農業協議会(生産)、農家レストラン(活用)のトライアングルで、それらの中心に「伝統野菜で地域活性化」という一貫したテーマがある。「地域活性」という言い方自体に魅力を感じたことはこれまでなかったけど、それは表層的なものを扱う事例しか知らなかったから、ということがよくわかった。三浦さんの取り組みは、自然と人、地域と人、人と人、人の外側と人の内側をつなぐ、本質的な地域活性だった。
また、「清澄の里 粟」の環境は、屋号の「粟」のコンセプトである「あ:はじまり」と「わ:調和」が、見事に体現された場だった。田の神様、在来種のヤギ、一年中ほとんどずっと一緒にいるという陽子さん、室内に入ってくる蜂、テーブルに並べられた伝統野菜、野菜アートの冊子、柿の木、見渡せる風景、畑、そして三浦さんの人柄、すべてがはじまりのようであり、調和のようであるもの。この全体性は、まさに「アートなるもの」だと感じた。これを目の当たりにすると、「アートで地域活性化」というのは言い方として成立しないことがわかってくる。このレポートにあたって、三浦さんの事業スキームをアートに応用できないかと少し考えてもみたけど、どうもしっくりこない。
三浦さんが提唱する「自給的生活」は、三浦さんの実践する食だけでなくても、エネルギーや住屋、学び、生業、健康、助け合いなどを入り口にすることもできるという。それは、税金やサービス料を支払うことで他者に委ねてきたことを、自分たちに取り戻すことと言えるだろう。それが豊かさと幸せにつながる。これは多くのアートプロジェクトと共鳴する考え方である(そもそもアートプロジェクトは脱近代を試みる表現形態なので)。
「自給率」という切り口で見た時に、「アートの自給」というのも考えては見たものの、やはりこれも言い方として成立しないことがわかる。アートは手段でも目的でもなく、豊かさと幸せに向かうやり方(これが何であれ)の全体性の中に立ち現れる現象のことではないだろうか。
LECTURE OUTLINE
三浦雅之&ラナシンハ・ニルマラ
2020年10月28日(水) 14:00–16:00
奈良の中山間地である清澄の里で、在来作物の調査研究・栽培保存に取り組む農業家の三浦雅之さんに「Project 粟」についてお話いただきながら、地域に根ざすプロジェクトを通して世代とコミュニティをつなぐ自給的生活文化の継承と創造について読み解きます。また、コメンテーターとして、スリランカの在来資源の価値を掘り起こす取り組みについてフィールドワークしている観光社会学者のラナシンハ・ニルマラさんをお招きします。
1970年京都府生まれ、奈良県在住。1998年より奈良県内の在来種の研究や栽培保存を始め、2002年に大和の伝統野菜の発信拠点、地域の交流の場として農家レストラン「清澄の里 粟」を開業。大和の伝統野菜の第一人者として第6次産業による事業に取り組んでいる。
1983年スリランカ生まれ、奈良県在住。観光社会学、南アジア地域研究を専門とし、主に地域社会の独自性と主体性を重要視しながら、観光を活かした地域活性化や持続可能な開発を研究している。JICA奈良デスクと協力して、SDGsへの認識を高めるための活動も行う。