REPORTS
- レクチャー
中村政人&西尾美也「ソーシャルダイブ/街を開拓する新しいアーツプロジェクト」
2021年1月30日(土) 14:00–16:00
奈良県立大学 CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
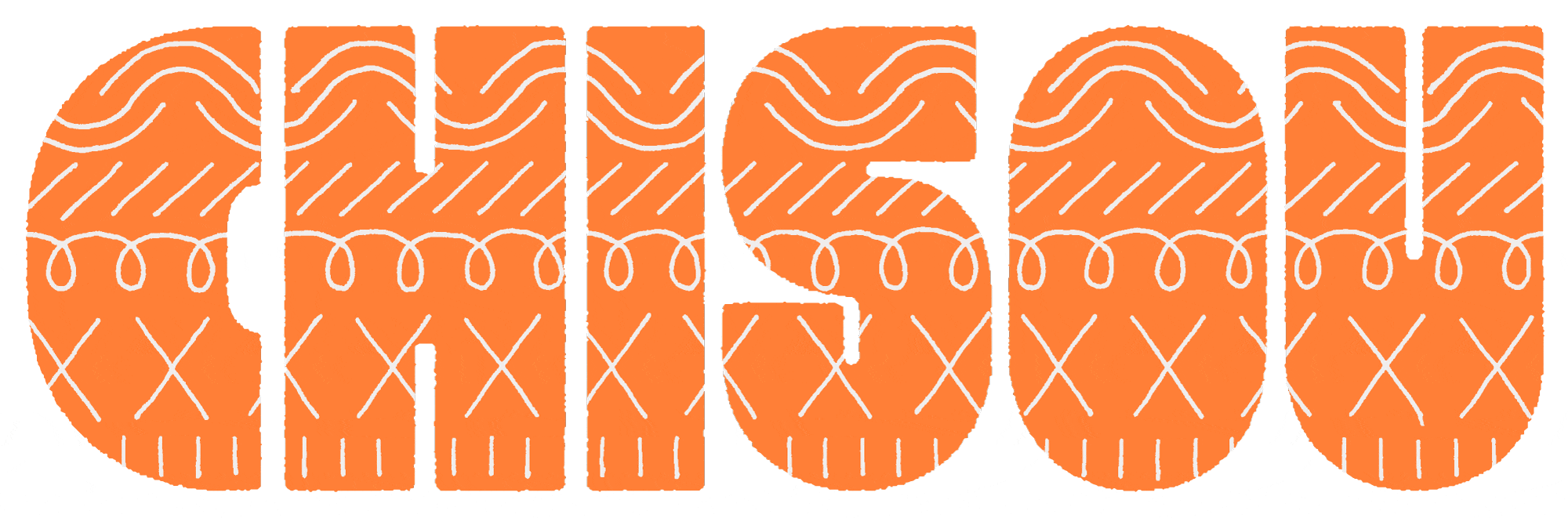
REPORTS
2021年1月30日(土) 14:00–16:00
奈良県立大学 CHISOU lab.
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

読解編の最終回は、国内外の展覧会でアーティストとして作品を発表するかたわら、アートプロジェクトの第一人者として全国各地でプロジェクトを展開してきた中村政人さんをお招きし、具体的な実践の経緯や手法、舞台裏についてお話を伺いながら、地域を読み解
きコミュニティと協働してまちに新たな日常を生みだすアートマネジメントの技法について思考を深めました。
CONTENTS

ウォルター・デ・マリアの作品で、約六メートルの長さの金属棒を垂直に百六十七本、深さ一キロメートルまで地中に埋めていき、最終的に地表には直径約8センチの金属の平らな丸い面だけが見えているというものがあります。一九七七年にドイツのカッセルで開かれた国際芸術祭「ドクメンタ」で約五千万円かけてつくられましたが、今も残っていて世界中の人が見にやってくる。僕は学生の頃にこの作品の写真に出会い、衝撃を受けました。こんなことが許される世界があると。絵を描く先にはこの世界が待っていると、夢をもつことができました。実際に触ると、地中の先にずっとつながっているという感覚をうっすらと感じる。見えないものに対してその存在を実感する。このプロジェクトに関わった皆でそのメッセージを組み立てようとした思いを、僕はひしひしと感じました。その思いを実現するプロセスそのものに、今日お話するアーツプロジェクトの大事な考え方があるのかなと思います。
僕にとってアートとは何かというと、対象や自分自身が考えていることに対して「純粋」になること。その純粋な思いをもって「切実」に向かい合い、つくることが生きることであること。その結果、生まれてきたものや出来事が、いつも見ているものから一瞬でも「逸脱」すること。純粋で切実な表現力が、絶望をエネルギーに変え、逸脱を促す。本当に苦しくなって自ら命を絶つ人たちもいる時代に、絶望的な気持ちに対しても表現はある瞬間エネルギーとして一歩前に進み生きる力を与えることができる、創造的なプロセスではないかと思っています。
今日はマネジメントを志す人や文化政策を担っている人などいろいろな人がいますので、どのように考え方を発展させていくかについて話したいと思います。「気づき」を形にする力がすごく大事です。どんな仕事でも、どんな人でも、「これは面白い」とか「こんなことやってみたい」と思う瞬間がある。これから起こることや思い描くことについて、ヒントになることが現れた瞬間がすごく大事で、この気づきを起こす瞬間をつくるために、様々なアーツプロジェクトは機能していると考えています。
一般的なPDCAサイクルでは「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」ですが、僕はこれをアーツプロジェクトに応用して「C」と「A」の部分を「Critique(批評)」と、「Awareness(気づき)」という言葉に変えています。いかにして気づきを形にするのかは、「A」の部分がいかに起きて、それがどういう流れになるのかということを実践的に考えていくヒントになると思っています。僕はまず「C」の批評から始まっていくと考えていて、物事を観察していく際に「前のものとちょっと似ているな」とか「見たことがなくて新鮮だな」とか、批評的に見ていくところから「このことが良いかもしれない」とか「可能性があるかもしれない」という気づきが訪れる。
どんな場所にでも、今は発芽していないけど水をあげると発芽していくようなことが多くありますが、そのような地域因子を批評的視点で発見し気づいた時に、「ここは面白くなるぞ」と創造的なきっかけが生まれます。その気づきをベースに計画をつくり、企画やチームをつくりながら、ビジョンを具体的に形にするためのアクションを実行してみる。実行すると計画通りにいかない部分が多いですが、次回はここに注意してこんな感じでやりたいとか、批評に対して次の動きが出てきます。このように気づきを誘発するための思考と創造の流れをCAPDの順で考えて何度も繰り返していく必要があります。
次に、価値を形成する重要な五つの力についてお話します。将来こんなふうになりたいとか、こういうことをつくりたいとか、「ビジョンを描く力」。それを実際にマネジメントして経済的に自立させていく「運営する力」。その背景には「気づく力」も必要です。計画の組み立て方によって実現度が変わるため、「計画する力」。コミュニケーション能力が基本的に重要なので、「つながりを生む力」。この五つの力のバランスをもって、CAPDをつくっていく。もちろん一人ではできません。僕もついついお金を使いたくなる癖があるので、経営的に苦しくなった時に「我慢してください」と言う人が必要で、会計的な知識や計画する力をもっている人とチームを組む。アーツプロジェクトは、いかにバランスをもってチームをつくるかというのが非常に大事です。
「東京ビエンナーレ」をやろうと僕が言いだして、一人百万円ずつ出し合ってシードマネーをつくるとなり、何人かの人が一緒にやろうと応援してくれました。そこからスポンサーを取ってくるプロデューサーはこの人にお願いしようとか、地域の人間関係はこの人にお願いしようとか、声をかけてチームをつくっていく。国際芸術祭として続けていくためには税制的な面にも対処しなければならず、しっかりと会計業務をして運営体制をつくる。他にも町内会で何かイベントをするのでもいいし、アーティストが自分の作品を制作するのでもいいので、思考のプロセスとしてプロジェクトという概念をもつと、様々なことに対して思考の幅や人間関係が広がります。

基底には地域因子という地域の宝となるDNAがあります。このDNAが発芽すると、その地域のサステナブルな文化や芸術の価値が生まれてくる。DNAに対してビジョンをつくり、そのビジョンを具体的にアクション、すなわち実行する。小さな活動だとしても、先ほど述べたCAPDサイクルを持続的に地域因子に対して続けていく。植物に水を与えて育てる気持ちで何年かつくり続けると、その人の心の中やコミュニティの中に「このことは地域にとって、自分にとって良い感じになってきたよね」というような気運が高まってくる。文化というのは、自分たちの場所から、自分が関わったなかで少しずつ芽生え、段々と認知されてきたり、良いねと言う人が増えてきたりします。
秋田の大館市では「ODATE」を「0/DATE」(ゼロダテ)と読み変えて、もう一度ゼロの視点から大館を見つめてみようというプロジェクトを十数年間してきました。「このまちで生まれ育った私は何か私ができることで、このまちが元気になることをしたい。このまちと共に成長したい。私が学び、受け継いできたことを子どもたちへ伝えたい。郷土に誇りと夢をもって生きていきたい」という思いでしたが、後半は正札竹村という百貨店のキャッチコピーでした。周辺のバイパス沿いに大手スーパーができ、ドーナツ化で中心市街地が陥没化して、大館市のシンボルだった百貨店が閉店してしまった。市民活動として何かできることがあるのではという思いから、最初はその百貨店の看板を外して、東京のギャラリーに持ってきて、同じ高校出身の東京にいる3人が集まって「ゼロダテ」という活動を始めました。この看板をベースにして、正札竹村の残ったものを作品化した展示を開催すると、二百人くらい秋田の人が集まって涙しながら見ていた。これは動かないといけないとなり、実行委員会をつくって高校の同級生に「シャッターを開けようよ」と声をかけました。少しでも動きをつくろうとまちに呼びかけ、新聞に広告を出したところ、デパートの前には大勢の人が集まった。心を開いて自分の存在を感じることのできる小さなコミュニティがこの街には必要ではないかと思い、なんとかして活動しようと思いました。
例えば、シャッターが閉じていた精肉店を一時的に展示会場にしたり、家具屋を市民のギャラリーにしたり、インターネットカフェだった空店舗をゼロダテアートセンターにしたり。十数年も活動していると、活動を共にしてきたスタッフが次のステージに進んでいくということで、区切りがついてきています。その中で、うまく活動のバトンタッチができたプロジェクトの一つが、オナリ座という映画館を再生するもの。閉じた映画館に高校生が入って皆で掃除している時に、35ミリの映写機がまだ動くことがわかり、これを使ったイベントを行いました。大家から暫定的に時間単位で借りただけで、すぐまた閉じてしまったのですが、何年か続けていくうちに千葉からここを借りるという方がやってきて、大家と交渉の末、貸してもらえることになりました。オナリ座自体が再生し、今でも運営されています。僕らがしたことは、オナリ座という地域因子に対して、「こんなふうに運営されないか」というビジョンと、掃除などの具体的な最初のアクションだけですが、活用する事例を見せることで、実際に借りる方が出てきて映画館は再生しました。
市民と共に芸術祭をつくる。「ゼロダテ」は、経済的にはNPOとして小さな予算での活動なので、東京のようにスタッフが入れ替わり来るような状況ではなくてとても苦しいです。でも、十数年続けてきて一つの成果は見えたんじゃないかと思っています。いずれにしても、地域因子の近未来を予知するかのように、アーティストをそこにマッチングさせて、そのマッチングさせたところに一つ活動や創造性、ビジョンが生まれてくる。そのビジョンを感じ取り、次へ一歩進む。そういうことが大事ではと思っています。
富山県の氷見市での「ヒミング」という活動についても紹介します。僕がつくるプロジェクトには必ずまちの名前をこっそり入れていて、これも「氷見」と「ハミング」をくっつけている。番屋と呼ばれる漁師が休む小屋をカフェにしたり、アーティストがまちに一週間くらい滞在して気になったものを映像で撮影してその場で編集しまちの人たちに見てもらう「氷見クリック」というローカルなテレビ局みたいなものをやったりしています。そもそも、なぜ氷見に行ったかというと、民事再生で負債を抱えた旅館を再生してくれないかと藝大の同級生から無理難題を言われて行ってみたら、お刺身が美味しくて……その美味しさと酒に「いいか」となり受けてしまった。旅館を再生するためには、まちの面白い人たちが面白いことをしないとまちに人は来ないよねということで、面白い人たちに面白いことをやってもらおうという作戦を旅館でしているところです。
そのためのきっかけの一つとしてアーティストがまちに入ってくると、嗅覚が鋭いため、いろいろなものに対して「これ面白いぞ」と言ってくれる。例えば、「氷見クリック」では、あるアーティストが川と木造の和船に着目して、この和船でちょっとした冒険旅行をする映像作品をつくりました。その時に気づいたのは、船って今はプラスチックでできていて、木造和船がないこと。そして、海に港が新しくできたことにより、古い番屋も使われなくなり、もはや川漁を中心とした河川文化がないこと。では、山と海をつなぐ川というものに焦点を当てるプロジェクトをつくろうとなり、「天馬船プロジェクト」が始まりました。
間伐材を用いて千艘の小さな船を皆で削ってつくり、上流から下流に流して最初にゴールにたどり着いた船が一等賞だというレースをする。ブログで一艘千円の寄付を募ると、百万円ほどの資金が集まりました。その資金の半分は木造和船を再現するために、もう半分は運営費に充てました。数回実施した頃に、一艘の木造和船ができあがりました。番匠さんという船大工がいて、日頃はFRPで船をつくっており、木の船をつくることはずっとしていなかったのですが、やってみたいと言ってくれました。やはり体が覚えていてつくれるんだなと感動しました。船をつくる木を山から持ってくるために森林組合の人も協力してくれて、急な斜面にグニャっと曲がりながら垂直に生えている杉の木を探してくれました。漁業組合と森林組合が協働して天馬船をつくろうとなったことが、大きな成果です。
ここでいう地域因子は、木造和船でもあるし船大工、つまり人に宿る技術や思い、精神でもあります。二艘の木造和船をつくり棟上げ式もして、今では毎年春になると遊覧体験があって、五百円払うと乗ることができ、氷見市の観光的資源の一つになっています。また、この地域因子が本質的なプロジェクトになったことで、漁具倉庫だった建物を皆で掃除してアートセンターにすることにもつながりました。ここにアートがどのように関係しているかというと、アーティストの特別な造形的センスや神秘性、付加価値などでは全くない。川や木造和船、技術、そこに宿る思いを、環境に負荷をかけない手法で、純粋に切実に形にすることを目指してコミュニティが生まれ、そのコミュニティの中に創造性が派生している。「ヒミング」というコミュニティ自体が創造的になったことで、「天馬船プロジェクト」という逸脱が起きたのです。
「ヒミング」の活動も十数年が経ち、中心メンバーが五十代、六十代に突入してきたので、続けていくことはなかなか難しいですね。理想的に世代交代がなされて、次の世代の人たちが自分たちのビジョンとアクションをつないでいくことができればよいのですが、やはり中心になる人にはお金を持続させていくことの難しさがあります。そこが小さなNPO活動の難しさですね。

仲間たちと「コマンドN」というチームを結成して東京の神田に拠点をつくり、家賃をシェアしてギャラリーを開きました。いろいろな作家を誘って自分たちで企画して展覧会をつくるのですが、この活動の特徴はセルフビルド、つまり自分たちで場所を全て施工していくこと。他の人にお金を払ってやってもらうのではなく、自分たちでやった方が楽しいでしょ。秋葉原の真ん中に事務所を構えていたのですが、千代田区に「隙間を貸してくれ」と交渉し、家賃はタダでした。活動の軸は、ネットワークをつくり、まちの中で展示をしていくこと。ゲストを招く時にはワインを出して、海外の人だと通訳もつけて、真剣に話を数時間かけて聞く。ファックスで呼びかけると、一つの価値のもとにコミュニティが吸引されるように皆がワイワイ集まってくる。これを四十回以上やりましたね。一つの興味や関心を通して一回でも心がつながると、そのネットワークは成長していくので、この時にやった活動は本当に大事だったなと思っています。
「秋葉原TV」というプロジェクトでは、秋葉原の販売用テレビをジャックして、ビデオアートの作品を上映したのですが、この場合の地域因子は秋葉原のテレビですね。このテレビの存在に気づいた時、無数にあるテレビをジャックして映像を流したらどうなるだろうかと考えた。その気づきを形にするために「コマンドN」というチームと場所をつくり、自分たちで企画を繰り返しながら実力を高め、秋葉原電気街の人たちに声をかけて実現しました。実は「コマンドN」は当時、僕も含めて全員ボランティアで、スキルや技術をシェアすることで人件費をぐっと抑えて、やりたいことの価値を共有していた。「秋葉原TV」では学生も含めて毎日三十人くらいのボランティアが出入りしていて、その人たちの熱量によってプロジェクトが形づくられていった。当時のボランティアスタッフで、今は「3331 Arts Chiyoda」の主役であり出資者でもある宍戸遊美さんという女性スタッフがいますが、先輩と後輩が一つの場所にいて自然に教え合うということが生まれてくると、活動は広がりや実現力が増してくる。その後もずっと、自分たちの手で自分たちの場所をつくり活動を生みだすということをポリシーにしています。

「3331 Arts Chiyoda」は、秋葉原の元中学校を改修した文化施設です。日本には美術館はたくさんあるのに、なぜアートセンターがないんだという批評から生まれました。世界中を回ると、地元の人が発表したり、無名の作家でも実験できる場所があるのに、なぜ日本にはないのか。そんな思いから計画的にこの場所をつくっていきました。
最初に設計した際には、地域に開くことをベースにしているため、「モノではなくて出来事をコミッションしていく」という考えを前提に、日比野克彦さんや藤浩志さんのような出来事をつくっていくアーティストに対して、立ち上げからずっと一緒に続けられるアートプロジェクトを計画してくださいとお願いしました。日比野さんには「明後日朝顔プロジェクト」、藤さんには「かえるステーション」をつくっていただきました。
この場所の歴史的な経緯と基層文化を大切にしながら、その上に新しい一層の文化をつくっていく。そのためには当然ですが、地域の活動に参加していくことが重要です。僕は地域のファミリー会に毎年参加して三百人前のきりたんぽをつくります。祭りも本当に素晴らしくて、祭りに寄り添うことが「3331 Arts Chiyoda」を成功させたと言っても過言ではありません。クリエイティブハブとしての機能をもっているので、海外から来る人、電車に乗って来る人、歩いてやってくる地元の人、それぞれに向けたプログラムを設計しています。このプログラム自体の魅力がその人に宿る創造性を喚起し、つながりが広くなることでコミュニティの創造力になり、都市の創造力が豊かになってくるという考え方をベースにしています。
運営面での流れについても触れたいと思います。僕のわずか二十万円の資本金で合同会社コマンドAを設立し、コンペに出したところ、一位の会社がリーマンショックでなくなってしまった。そこで僕らが浮上して「3331 Arts Chiyoda」を始めることができ、資本金を増やしながら運営して今に至ります。通常の文化施設では、自治体が指定管理者である企業などに指定管理費を払い、その指定管理者が運営していく場合が多い。この指定管理の仕組みを脱して、3331 モデルという自律型アートセンターのビジネススキームをつくったことが重要です。区からは「文化施設をつくってください。ただし自力でつくってね」というような、全国にも例がないやり方で、合同会社コマンドAは区に家賃を支払っている。人件費を賄うために、有料の活動プログラムをつくって収益を上げて持続させている。商業施設の発想ではなく文化施設としての発想でつくらなければならないので、当然ですがアーティストが展覧会をしたり、地域の人が表現したりしやすくなるようにファシリティとクオリティをコントロールしています。約数億円の収入があり、支出もそれくらい。通常だと指定管理で数億円を行政からもらって運営し、年間約千本のイベントをつくり現在の約八十万人の来場者を集めるのでしょうが、それを全て自己収入で賄っていることが全く新しいことですね。
実は「3331 Arts Chiyoda」を立ち上げる時の企画書に「東京ビエンナーレ」と書いていて、最初から「東京ビエンナーレ」をする前提で「3331 Arts Chiyoda」をつくっていました。「3331 Arts Chiyoda 」を点とするなら、「東京」という言葉はエリアになるので、「東京ビエンナーレ」ではエリアとしていかに個人に宿る創造力を解凍し拓いていくかを考えています。そのためには、まちの人たちが受けとめる力が必要です。まちの人たちとの関係をつくりながら、過去と未来をつなぐプロジェクトを生みだし、江戸・東京の基層文化に新しい文化層をつくりだしていきたいと思っています。二〇一八年に「構想展」をつくり、作家たちに「こういうことやりたいんだけど、みんな何か面白いこと考えようよ」と声を投げかけ、二〇一九年にどのように計画するか「計画展」で発表するように投げかけ、本当なら二〇二〇年の夏に実現するはずだったのですが、コロナで一年延期になりました。
「計画展」で作家のプロジェクトが絞り込まれ、予算感など具体性を帯びてきたところです。優美堂という額屋さんで僕が進めているプロジェクトについて少しお話しますね。ここは防空壕のある建物で戦後すぐにオープンした店なのですがシャッターが閉まっており、なんとかそこを再生したいと思って大家さんに交渉しました。大家さんはこの建物を壊してビルを建てようという発想もあるなか、五年間だけだったらいいぞと協力してくれました。建物の中には大量の額が詰まっていて、この額を使ってプロジェクトを展開できないかと考えているところです。
このようなプロジェクトをしていく時に非常に大事なのが、寛容性と批評性です。まちの人たちにも僕らにも受けとめる力があれば、言う側は忖度せずにはっきりと表現を打ちだせる。でも受けとめる側が「いや、それはちょっと困るな」とか、「そんなことしちゃったら、これはこうでしょ」というふうに受けとめる力がどんどん弱まり、言う側も「ここまで言うのはやめて、これくらいにしておこう」となり、「それだったらお金はこのくらいかかりますよ」というように、純粋で切実で逸脱から逆の方向にどんどん向かう。アーティストと市民の協働で東京に国際芸術祭を実現する「東京ビエンナーレ」はこの寛容性と批評性へのチャレンジだと思っています。政治的に考えると四区が関係しているのですが、区が非常に力をもっているため行政が主導でやるのは至難の技で、国や東京都が本気でやらない限りは起きにくいと実感しています。それに対して、市民が立ち上がりボトムアップでつくっていくのは、自由度をもって設計できるので本当に楽しいです。
ゲニウスロキという言葉は、「地霊や歴史、風土、産業など様々に蓄積されたその地域の気配や魅力」を表していますが、「この辺り、なんか雰囲気いいよね」という感じです。その雰囲気を醸しだしているのは、建築や石碑、道、技術、歴史、人など、ゲニウスロキを感じる様々なポイントです。そのポイントが再開発でどんどん見えなくなってきており、さっきの優美堂の建築はまさにそれなんです。ゲニウスロキや歴史的な基層文化の流れを感じとるものがなくなってしまうことに対して、新たな新陳代謝を促していくことが大事です。

フランスの社会学者ピエール・ブルデューが唱える文化資本には三つあります。一つ目は客体化された文化資本で、書籍や絵、骨董品など有形でお金で買うことのできるもの。二つ目は制度化された文化資本で、学歴や資格、免許など、制度が保証してくれるもので、本人の努力によって得ることができる。三つ目が重要ですが、身体化された文化資本。礼儀作法や慣習、言葉遣い、センスなど、買うことによっても本人の努力でも身につかないもので、その地で生まれたことによって宿ってしまうもの。自然と身につく身体的文化資本は、学校教育では身につけられない。文化資本の蓄積には長い年月が必要ですが、数百年かけて蓄積した文化資本でも消滅すると価値は一瞬にして見えなくなってしまう。

レクチャーの冒頭、中村さんから「アートとは何か」と問いかけられた。これまで私は、アートとは人に気づきを与えるもの、新たな視点を得ることができるものだと考えていた。さらに言えば、そこには「わかる人にはわかる」「気づく人だけ気づけばいい」という、作り手側の思いが優先される構図があると感じる機会もあり、そうした関係性にどこか閉塞感を覚えていた。だが、アートをプロジェクト化する事例や考え方を学ぶことで、アートという「概念」をアートプロジェクトという「出来事」の視点から捉え、それに関わる人の創造性を刺激する効果もあると感じるようになった。事例紹介では、中村さんがまちの人たちと一緒に、ビジョンを描きながら行動する様子が見てとれた。アーティストではなく、周りの人たちが主役となっている姿に、これまでのイメージがよい意味で壊された。今回のレクチャーを通して、自分がアートに関わっていく際の思考や行動の幅をさらに広げてもらえたと感じている。(古江晃也)
わざわざ新しく何かをつくるのではなく、地域の人々が暮らしの中で自然と身に付けてきた素養に気づき、彼らがつながる出来事をカタチにする。ゆるやかに始まり、やがて地域の中で自発的に継続されていく、そんないくつかの創造的イベントの事例の話を聞いて、あるがままにある何かに新しい価値を生みだすのは、「気づきをカタチにする力」であると感じた。(山本篤子)
アートには様々な形態のものがあり、また「ここまでがアートでここからは違う」という明確な線引きが難しい。だから「アート」という言葉が、それ自体をわかりにくくしてしまうことがある。中村先生から「アートとは何か」と問われ、私は「規定しないもの」と答えた。アートの意味を定義することよりも、その概念について多様な答えが生まれる、そんなプロセスにこそ価値があると感じている。(早田典央)
新型コロナウイルスの影響でなかなか思うように動けていないが、今年度は大学でサバティカル(研究休暇)を取得している。東京オリンピック関連の文化イベントのあり方について実践者の立場から考察することが一つの研究テーマだ。加えて、「CHISOU」のことや奈良での今後の展開について考えたい。そうした学びを求めて、中村政人さんにサバティカルの受け入れ先になってもらっている。
小林瑠音さんのレクチャーのところで、アートプロジェクトの「普及」版といった表現について言及した(p.162)。実際こうした催しとそこでつくられる作品を「地域アート」と名づけ、アートプロジェクトがカウンターとして提示された時には斬新であったとしても、このままでは「地域を活性化するもの」こそが「現代アート」であるというふうに、定義の方が変化していくと指摘する批判もある。中村さんが「地域アート」という言葉さえ使いたくないと言われたのは爽快だったが、中村さんがアートの定義として掲げる「純粋×切実×逸脱」は、確かにこうした批判に圧倒的に対抗する考え方であり、実践と言えるだろう。
実際に、「東京ビエンナーレ2020/2021」にも作家として参加するなかで驚いているのは、多数いる各作家の個別ミーティングにさえ中村さんがすごい頻度で参加するということ。地域の祭りにも参加するように、共に居ることを通して、中村さんは自らの「身体的文化資本」を発揮し、磨いている。この身体的文化資本について、平田オリザは、「センス」あるいは「様々な人々とうまくやっていく力」と言い換えている。中村さんの様々な実践から感じられるのは、アートプロジェクトは、人々がこのセンスを身に付けるためにこそあるのではないか。
これから筆者が着手しようとしている「美術は教育」プロジェクトでは、脱美術館的=脱権威的な活動としてのアートプロジェクトの最終目標を、すべての人が創造的である状態に向けて働きかけることだと仮定し、その「学びの共有空間」としての可能性と課題を明らかにする。アートマーケットやアートワールド、あるいはまちづくりや地域振興といったわかりやすい目的に回収されないアートプロジェクトの価値について言説化することを目指す。そして、中村さんの『美術と教育』(1997)、『美術の教育』(1999)、『美術に教育』(2004)に次ぐ、『美術は教育(仮)』として刊行する計画である。
LECTURE OUTLINE
中村政人&西尾美也
2021年1月30日(土)14:00-16:00
※中村政人さんはオンラインで参加いたします
1963年秋田県生まれ、東京都在住。国内外の展覧会や国際展で作品を発表するかたわら、地域コミュニティの新しい場をつくりだすアートプロジェクトを多数展開。近年は「アート×コミュニティ×産業」の新たなつながりを生みだすアートプロジェクトを進めている。
1982年奈良県生まれ、同在住。装いの行為とコミュニケーションの関係性に着目したプロジェクトを国内外で発表。近年は公共空間へアプローチを行う大規模な作品に取り組む。奈良市アートプロジェクト「古都祝奈良」ではプログラムディレクターを務めている。