REPORTS
- レクチャー
藤田瑞穂「キュレーターは何を編集し、アーカイブしているのか」
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
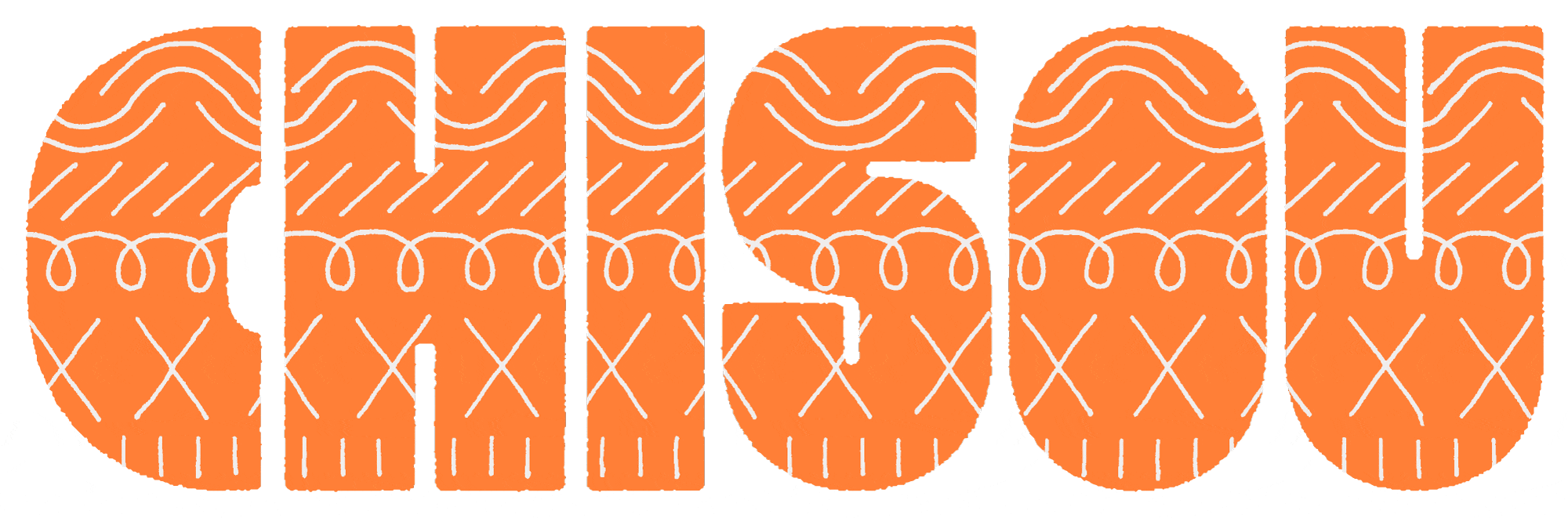
REPORTS
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
京都市立芸術大学の附属ギャラリーである@KCUA(アクア)で、先駆的な展覧会企画を数多く手がけてきた藤田瑞穂さんをお招きし、ウェブサイトや書籍などによる展覧会の記録から、大学の収蔵品や地域の資料の創造的活用まで、キュレーターの視点からアーカイブ実践について掘りさげてお話いただきました。
CONTENTS
一口にアーカイブと言っても、作品や資料などをアーカイブするのか、アートプロジェクトのように形がないものを残すのかによって、そのあり方は様々です。すごくわかりやすい例を一つ、紹介します。以前、作品や資料を収蔵し、保存・研究を行う博物館施設の学芸員と、お互いの仕事について話をしていた時のことです。その方が「私たちの仕事は、飛んでいる蝶を追いかける仕事ではなく、蝶が飛んでいる時にはずっと待っていて、動かなくなった時にそっと拾って標本箱に納める仕事です」とおっしゃったんですね。その喩えがものすごく心に響きました。私は学芸員という肩書で仕事をしているけれど、一般的なそれとは何かが違う気がする、とずっと思っていたのですが、その一言で、私のやっていることは飛んでいる蝶との仕事みたいなものだったんだとすっと腑に落ちたんです。というわけで、これから私がお話するのは、博物館などで扱われている有形のコレクションとしてのアーカイブではなく、生きたままのアーカイブについて、ということになります。
大学では美術ではなく比較文学を専攻していました。比較文学を専攻したそもそもの理由は、文学を言語や国で分けることに対して違和感があり、もっと違う考え方で文学に接したいと思ったからでした。大学院への進学を考え始めた頃、私は、ソ連出身のイリヤ・カバコフという非常に物語性の強い作品を手がけるアーティストについて研究したいと考えていたのですが、それだと「文学研究」にならないのでは、と悩んでいました。そんなある時、指導教官と同級生とで世間話をする機会がありました。就職活動をしていた同級生の「面接で比較文学がどういう学問なのか尋ねられても上手く答えられない」という話に対して、先生は「日々、人は過去の出来事を思い起こしたり、無意識のうちに現在と過去を比べたりして、過去の影響を受けながら生きています。そういう意味では、人はこれまでの人生で比較文学的なものの考え方に出会っていると言えます」とお答えになりました。私はその一言にハッとしました。人生が比較文学のようなものだとしたら、研究対象は必ずしも文学作品でなくても良いんじゃないか。それで、悩むのをやめてカバコフの研究を始めることにしたんです。我ながら都合の良い解釈だな、と思いますけど。
カバコフは、現在のウクライナにあたる地域のユダヤ人家庭に生まれました。モスクワの名門の美術学校に合格し、「絵画科」よりは格下とされた「グラフィック・アート(線画)科」に進学したカバコフは、在学中から卒業後の約三十年間にわたって絵本挿画の仕事に従事することになります。また、生きるための手段としての絵本挿画の仕事とは別に「非公式」の芸術家としてモスクワ・コンセプチュアリズムというグループで活動を続けました。カバコフ自身が「アルバム」と呼ぶ、テキストとイメージが描かれた紙の束からなるストーリー仕立ての作品をいくつも制作し、それをめくりながら朗読する形で、仲間内で「非公式」に発表していました。やがてソ連を出てヨーロッパで活躍するようになると、彼は自分の作品の背景にあるソビエトの常識や日常がそこでは全く通じないことを実感します。そこで、ソビエトの日常を状況ごとつくり上げる「トータル・インスタレーション」と呼ばれる劇場装置のような作品を手がけるようになります。このように、その時々の状況の中でいかに生きて表現するかというカバコフの姿勢や瞬間ではなく流れを重視する時間の観念、作品のもつ物語性に、当時の私は比較文学的なものを漠然と見出していました。
しかし、カバコフ作品にのめり込み、彼の考え方に同調し過ぎてしまって、文学研究者を納得させる論を展開できずに研究が行き詰まってしまいました。そんな私を心配した先輩が「そのやり方は批評じゃない。批評というのは、海で泳ぐ人を岸でじっと眺めて考えるようなことだよ」という助言をくれたのですが、私は「岸で眺めているだけなんて自分には全く向いていない。私は一緒に泳いでいたい」と思っていました。
そんな時に『展覧会カタログの愉しみ』(今橋映子、東京大学出版会、二〇〇三年)の出版記念シンポジウムに 参加し、「田中恭吉展」(和歌山県立近代美術館、二〇〇〇年)のカタログについて担当学芸員の寺口淳治氏による発表を拝聴し、衝撃を受けました。カタログが単なる展覧会の記録を超えて、本が立体的なものとして動きだすかのように感じました。これこそまさに、作品やブックデザイナーと「一緒に泳いでいる」ということだと感激しました。そして、そんな本をつくることに憧れたのです。
しばらくして、定期的に発行していた研究室の紀要の編集委員を担当する機会を得ました。Wordなどのワープロソフトの原稿をそのまま印刷した簡素な冊子ではなく、テキストとイメージの力を引き出すデザインでもっと新たな論文集にしよう、と研究室のメンバーを説得し、一緒に改革してくれる熱きデザイナーを探しました。そうして出会った松本久木さんとは、それからずっと一緒に印刷物をつくっています。
本を楽しくつくることだけでなく学芸員の仕事への憧れも募り、博士課程の在学中に京都芸術センターで働き始めました。ここは演劇、ダンス、美術、音楽、伝統芸能という多様な芸術分野を扱う施設で、スタッフは自分の専門以外のジャンルの仕事も担当します。また、この施設は、アーティストの要望によって設立された経緯があり、催し物だけでなく、日々様々なアーティストたちが制作を行う「制作室」があることに大きな意味をもっていました。さらに、明治期に地域住民が自分たちの力で建てた元小学校の建物を活用しており、この場所で小学校を守り育ててきた地域との関係性も非常に重要でした。加えて、様々な活動がたくさんのボランティアスタッフによって支えられていました。私は様々な分野のアーティストの声、地域住民の声、ボランティアスタッフの声を聴き、ここで自分が何をするべきかということを常に考えて仕事をしていました。自分の置かれた環境で、そこにいる人たちと、どうすれば良い音が奏でられるのか。自然とそういう仕事の仕方をしていた気がします。
ここで、アーティストの柴川敏之さんとボランティアスタッフの方々と協働して、地域の人たちが大切にしてきた小学校の建物を見つめながら「2000年後の小学校」という展覧会をつくりました。柴川さんは本当にこだわりが強く、展覧会の記録集をつくっている時には、「一緒に泳ぐ」を通り越して溺れそうになりました。一緒に溺れながら泳いでくれたのが、デザイナーの仲村健太郎さんでした。仲村さんも、先ほどの松本さんと同じく、アーティストが誰であっても必ず気持ち良く一緒に泳げる仲間で、それ以後も協働して何冊も本をつくっています。本のコンセプトをじっくり話し合い、そこに流れる声や無形のものを表現するために、必要な紙やフォントを選びとっていく過程そのものが、動的で生っぽいジャムセッションのような感じです。
二〇一四年からは京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(以下、@KCUA)に勤務しています。大学附属ギャラリーというと、学生の作品を展示する施設を思い浮かべるかもしれませんが、@KCUAの活動はそれとは少し違っています。
キャンパスは京都の郊外にあり、@KCUAはまちなかのサテライト施設であるため、在校生の来場は少なく、卒業生や京都で活動するアーティスト、美術関係者、美術に関心がある一般客などが主な来場者層で、社会に開かれた大学の施設、あるいは社会と大学の間のような存在です。
@KCUAで実施する展覧会には、大きく分けると「特別展」と「申請展」と「大学事業」の三つがありますが、今日は学芸スタッフの企画による展覧会である「特別展」に焦点を絞って話します。「特別展」では、アーティストに併走しながら、作品だけではなく、それが立ち上がるところ、つまりアーティストの思考の過程まで感じられるような展示をつくることを心がけています。展覧会ごとに工夫の仕方は異なりますが、例えば、ジョーン・ジョナスの個展「Five Rooms For Kyoto: 1972–2019」(二〇一九年)では、作品の展示に合わせて、ジョナスが長年携わってきた美術教育の活動や、制作過程のアイデアスケッチなども紹介しました。
美術館だと数年前から丁寧に企画を練っていく場合が多いですが、@KCUAはごく少人数のスタッフで運営していて、企画の立ち上がりから展示に至るまでのサイクルがかなり短い。年間に担当する展覧会も、美術館だと数年に一回とかですが、@KCUAだと年に複数ある。でも、小さい組織だからこそのフットワークの軽さを活かして、今一緒に考えたいものを現在進行形で提示してきました。実験的なことをどんどん試みていく大学らしく、失敗を恐れずに挑戦することであらわれてくる生々しいものが感じられる場所にしたいと思っています。
そのように考えて展覧会やプロジェクトをつくってきましたが、いくつかのものに関しては書籍に形式を変えて蓄積しています。展覧会を実際に観てもらうことができるならそれが一番と思っていますが、その上で書籍はより深く長く何かを伝えられるもので、十年後に読んでも新鮮で価値のあるものにしたい。展覧会の記録というよりも、もう一つの形としてつくり直すという感覚で取り組んでいます。本の形だからこそできる魅力的なものをつくるために、デザイナーさんと二人三脚で毎回試行錯誤を繰り返しています。こだわりすぎて、展覧会終了からずっと後に発行されることもありますが、いつもワクワクしながら取り組んでいます。
京都市立芸術大学は二〇二三年に京都駅近くにキャンパス移転を予定しています。移転予定の地域は、都市計画のための整備事業が長年にわたり行われていたところで、移転計画が発表された二〇一四年当時、たくさんの空き地がありました。大学の先生たちと何かここでイベントをしたいと考え、閉校した元小学校の建物と周辺の空き地で行ったのが、私が手がけた最初の移転整備プレ事業「still moving」という展覧会です。芸術大学がこの地域にやってくる第一歩という位置づけでした。
国内各地から鑑賞者が来て、展覧会には多くの反響がありましたが、地域住民の来場はほとんどありませんでした。地域に通ううちに顔見知りになった方々は「がんばりや」と声はかけてくれたのですが。この展覧会は、地域への引越しのご挨拶でもあると考えていたけれど、地域に入っていくというのはそう簡単なことではないと気づきました。そこから、次にどうすれば良いかを必死に考える日々が始まりました。
その後も、移転後の大学の役割を考えるプロジェクトと、地域におけるプロジェクトを並行して行っていきました。地域では、例えば地域の方々が大事に守ってきたお祭りに、教職員や学生、卒業生とともに毎年参加するなど、とにかく顔を覚えてもらって、何か共有できるものを一つでも増やそうとしました。そうしていくうちに、私自身の中で地域に対する気持ちが段々と変わってきました。また、物事を見る目の解像度も高くなっていったように思います。
こういった小さな取り組みの積み重ねが、二〇一八年に手がけた「still moving documents」につながっていきます。プロジェクトの参加者と新キャンパスの建築チームと協働して、これからどんどん変わっていくまちのことを観察し、地域に通ううちに少しずつ積み重ねていったものを記録していくという取り組みです。地域が変化をするように、自分たちの活動や考え方も変化し続けて終わりがないというコンセプトから、制作した記録物は巻物状になりました。巻物の内側には私たちの記録を、外側には地域住民二人に小学校の思い出を聞き取りしたものをダイアローグ形式で掲載しました。元小学校の建物の解体直前のイベントを大学と地域住民が協働して行うなど、この六年間で大学と地域の関係性は少しずつ変化しました。そして、移転整備プレ事業のアーカイブそれ自体が、複数の小さな物語を紡ぐものになってきています。
キャンパスの移転計画は、こうした地域との関わりだけでなく、大学自体のあり方を考え直すきっかけにもなっています。郊外型のキャンパスから都市型のキャンパスへの変化は非常に大きなことで、今よりは開かれた場にならざるを得ないし、そのように求められてもいます。
京都市立芸術大学には芸術資料館という、教育研究活動のアーカイブを収蔵する機関があります。移転後の大学について考えていくなかで、大学の附属施設としての芸術資料館と@KCUA、それぞれ独自の機能を活かしつつ協働できないかと思い「京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品活用展(以下、収蔵品活用展)」のシリーズに取り組み始めました。例えば、「移動する物質——ニューギニア民族資料」(二〇一七年)では、ある物が本来あった土地から移動させられてまったく違う土地にやってくるということが、収蔵品や物質にどのような変化をもたらすのか。ひいては大学が移転した後に起こる変化について考えることにもつながるのではと思い、「物質の移動」という点に注目して制作しました。
「still moving library」(二〇一九年)では、教員が持ち寄った本と芸術資料館の収蔵品を用いて@KCUAに擬似的な図書館空間をつくりました。移転後のキャンパスでは、@KCUAも入る大学の発信地的なエリアの中心に図書館が配置される予定なのですが、それに対する先行実験として、人々が情報を「再編集」する場としての図書館を考えた試みです。
展示空間の一角に、@KCUAのアーカイブの「再編集」について検討していくためのスペースを設けました。プロジェクトメンバーの一員であるデザイナーの仲村健太郎さんと、毎週この空間の中でミーティングを開き、@KCUAに期待される役割とは何か、@KCUAのプログラムに継続的に関心をもってもらうには何が必要か、など様々なトピックについて議論しました。そこで、いろんな引き出しをつくっておいて、気になったらどんどん奥を掘っていけるシステムをつくったら良いのでは、とウェブサイトや年次報告書のリニューアルをすることに決めました。情報にアクセスしやすく、また興味をもった人がアーカイブにもアクセスしやすくなる仕掛けについて徹底的に話し合いながら作業を進めました。
開催中のものだけでなく、アーカイブにもアクセスしてもらえるように、トップページに「おかわりアクア」という機能を加えました。現在の展示や関心とも関連させて、過去のアーカイブを違う切り口で選んで見せる試みです。また、自分たちにとっても、過去にしてきたことを振り返りながら、今後どうしていこうかと考えるための俯瞰的な視点を与えてくれるシステムになりそうです。
展覧会の映像記録も始めました。映像や動きのあるインスタレーションだと、写真ではどうしても抜け落ちてしまう情報、例えば動きや音がわかったり、展覧会を体験する雰囲気をパッケージしたりできる。映像と写真だけでは十分ではないかもしれませんが、少しでも生っぽさを伝えるためには映像は有効だと思います。コロナ禍で実際に展覧会を鑑賞できる人が限られる状況となって、よりアーカイブについて考えるようになりました。今、自分たちにできることは、展覧会を生きた状態で生っぽく残すことだけですが、後々この取り組みが何か大きな意味をもってくるのではと思っています。
アートプロジェクトの記録・公開において大切なのは、わかりやすく伝えるといことに加えて、深く知りたいという⼈にはより詳細な情報を提供できる、そんな「柔らかい地盤」のように容易に掘り進めることができる環境だと感じた。また記録した情報を公開する際には、アート業界の視点ではなく、社会保障の問題や環境問題、ジェンダーについてなど、あらゆる視点からプロジェクトを俯瞰し、検証・分析することが必要であり、それによってより多くの⼈がプロジェクトに関⼼をもつようになるのではないかと考えた。(米田陣)
アーカイブとは、つくった人の熱い思いが見える生きものなのだと感じた。「プロジェクトや展覧会の記録物ということだけでなく、本そのものとしてどうかということを考え、もう一度つくり直す気持ちでつくっている」とおっしゃっていたのが印象的だった。その内容はもちろん、細部の構造まで心配りがされている本からは、つくった人の温かさが感じられる。プロジェクトに対してももちろんそうだが、本を大切に想い、愛する気持ちをもってアーカイブ制作を行いたい。(櫻井莉菜)
「アーカイブで何を編集するのか。」まるで謎かけのようにつながり、広がり続ける問いと答え。「何を」編集するかで、関心や興味に引っかかる「誰か」が変わる。プロジェクトの始まりから終わりまで、関わってくれた人の視点をできるだけ集めて整理し、魅力的に見せられるよう、周りの力を借りながら工夫できるといいなあ感じる人がいてこそのアート。愛と熱量を込めた、これまで関わってくれた人への「ありがとう」が、次の「関わりたい」の芽になりますように。(まさきまゆこ)
ハンナ・アーレントは、人間の基本的な活動力を、「労働」「仕事」「活動」の三つに分類した。「労働」は生命を維持するための行動で、「仕事」はある程度の耐久性をもつ消費の対象をつくる行動、「活動」は物の介入なしに人と人との間で直接交わされる唯一の行いであるとされる。この分類に基づいて、僕はこれまで一貫して、自分のプロジェクトは「活動」、それを展覧会で見せるのも、カタログにするのも、論文にするのも、あるいは服として販売するのも、すべて「仕事」だと捉えてきた。そして、「活動」こそが自分にとって最も重要なもので、「仕事」は副次的な産物だと捉えてきた。その意味で、僕にとって学芸員という存在は、仕事相手という認識にとどまっていた。
しかし、藤田さんの最初の自己紹介を聞いて確信するのは、アーティストが独自の表現を探求しているのはもちろんだが、そのアーティストに協働を呼びかける「誰が」という部分も当然一様ではないから、どのような問題意識をもった人であるかということが、その成果を決定的なものにしているということだ。学芸員は雑芸員と呼ばれて久しいが、一方で、独自の背景や問題意識をもった人が、何かを企てていく時に、学芸員という立場はすごく柔軟で有効なものになり得るということを藤田さんの実践は教えてくれる。
また、そうした「学芸員」とであれば、単なる「仕事」の仲としてではなく、展覧会にしろカタログにしろ何かを共につくるプロセス自体が、まさに「活動」的なものになるのだろう。アートプロジェクトのアーカイブ実践においても、「もう一度つくり直す」という意識と共に、それを「仕事」としてではなく、関わる人々の互いの問題意識を共有しながら「活動」としてできるかどうかが、すごく大事なように思わされた。