REPORTS
- レクチャー
Studio Kentaro Nakamura「翻訳とサンドイッチ──多を束ねること、他につなげること」
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
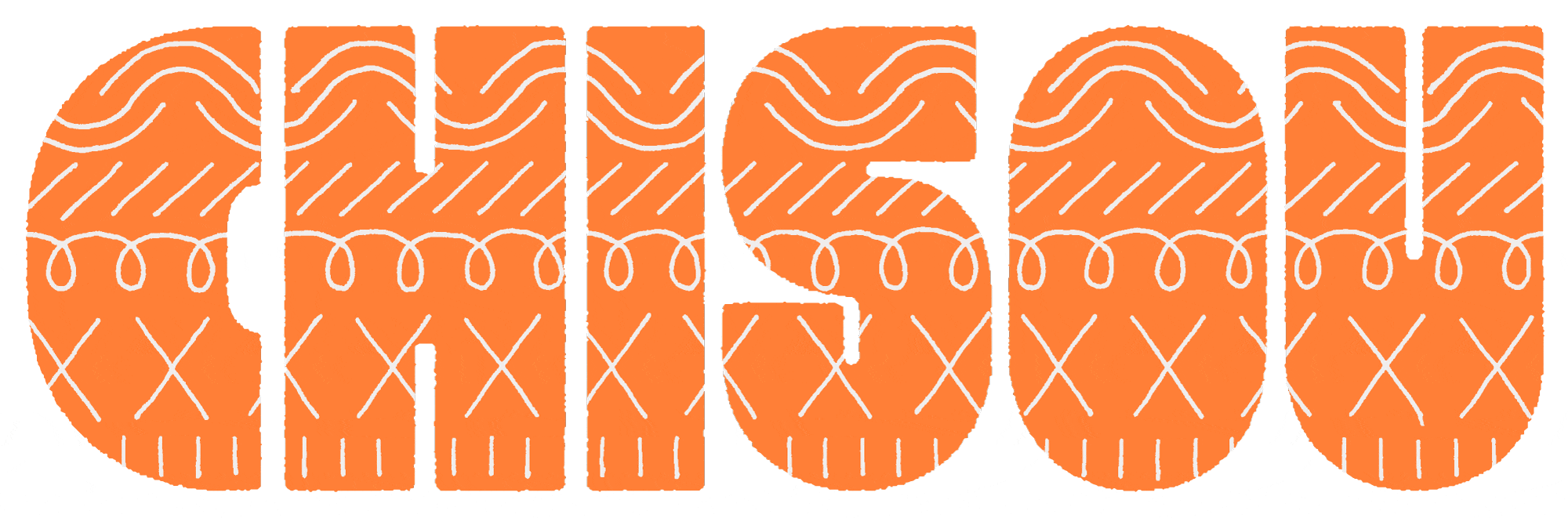
REPORTS
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
本や雑誌などの印刷メディアだけでなく、ウェブデザインといったデジタル表現も通して、美術や演劇など幅広い芸術分野のデザインを手がけるStudio Kentaro Nakamura の仲村健太郎さんと小林加代子さんをお招きし、多種多様な出来事や情報と向き合い、アートプロジェクトとアーカイブを紐づけていく技法について学びました。
CONTENTS
仲村 僕たちにとってグラフィックデザインの定義は、「不特定多数の人と視覚的な言葉でコミュニケーションすること」です。例えば、ポール・ランドは、「見る者にメッセージを伝えられなければ、優れたデザインとは言えない。メッセージをヴィジュアル化して人に伝える場合、ひと目で発信者の意図が理解されなくてはならない――それがどんな方法でも、相手に何か主張したいのか、それとも情報を提供したいのかに関わらず、大勢が目にする広告掲示板から個人的な出産報告に至るまで。つまり、美しく、目的に叶っていなければならない」と言っています。目的というのは、「見る者にメッセージを伝える」ということです。
今日、皆さんと考えたいことは、アートプロジェクトという言葉で説明しにくいことをどうしたら視覚的に他者に伝えられるのかということです。また、アートプロジェクトに潜む文脈は、果たしてアーカイブすることができるものなのかということも考えていきたいと思います。
仲村 デザイナーとは、発信する人と受け取る人の間にいる存在だと考えています。まずデザイナーは、発信する人と一緒にプロジェクトの言葉をつくります。そして、言葉をつくったら、その言葉を視覚言語に翻訳して、受け取る人に渡します。僕たちの場合、絵や画面をつくる作業は後者の作業になります。視覚言語に翻訳するというのは、一般的なデザイナーの仕事ですが、プロジェクトの言葉をつくるという作業はイメージがしづらいかもしれません。そこで、グラフィックデザインを視覚的な「メッセージの発信」、視覚的な「アーカイブ」、視覚的な「編集」として捉え、その考え方と実践してきたプロジェクトについてお話したいと思います。
仲村 まず、プロジェクトの言葉をつくることについて考えましょう。それぞれのアートプロジェクトには、固有のコミュニケーションの仕組み、つまり、固有の言葉があります。作家が違えば言葉が違うのは当たり前です。場所が違えば言葉が変わるのも当たり前。仕組みが変わると言葉同士の関係が変わります。言葉同士の関係が変わると言葉の意味が変わります。では、言葉の意味が変わるとはどういうことでしょうか。
外山滋比古さんが『新エディターシップ』(みすず書房、二〇〇九年)の中で関係価値について書いています。
言葉はひとつひとつの語としてもある程度は独立している。辞書の示している語義は、その語を抽象的にとり出し、独立させた場合の意味が中心になっている。孤立し独立した単位の意味を要素的意味と呼ぶならば、他と結合して生ずる意味は関係意味ということになろう。言語においては、前者のことを辞書的意味(レキシカル・ミーニング)、後者のこを文脈的意味(コンテクスチュアル・ミーニング)という。
例えば、「黄色」を辞書で調べると定義が出てきますが、「黄色い声援」だとその意味が全く変わってきます。「きゃー、きゃー」という文脈的意味が付け足されて、全く違う意味になります。アートプロジェクトにおいては、この文脈的意味がすごく大事で、辞書的意味はそこまで大事ではないと思っています。
単語は、ほかの単語と結びつけられると、個々の意味が変化する。複合語というような単純なものでなくて、文章とか作品の次元になると、その中でもつ各部分の関係意味はとうてい記述を許さないような複雑なものになる。
例えば、十七文字の組み合わせである俳句に感動するのはなぜかと言うと「関係意味」がすごく複雑だからです。十七文字しかないのに多くの意味が含まれている。同じようなことが、詩や小説にも言えます。ただ組み合わせただけで意味が変わるから面白い。そして複雑になるから面白い。
言葉が、記号としてきわめて微妙なものであり、複雑なことを表現できるのも、要素的意味よりむしろ関係意味の可能性が高度に発達しているからだという点に気付くはずである。そして、その背後には人間の頭に「関係付け」の能力が存在するのは言うまでもあるまい。人間がもっとも人間らしいのは、孤立したものを結び合わせる能力においてでなければならない。
つまり、外山さんは「関係付け」ていくと言葉の意味が変わると言っていますが、これを僕は「辞書的意味から自由になる」と解釈しました。断片的なものの中に新しいつながりや意味を発見することは、それを伝える立場の側においても、あるいは受け取る立場の側にも、どちらにも開かれた人間らしい豊かな行為だと思います。それは、俳句を読んで感動するのと一緒で、言葉のつながりに意味を見出していくことは豊かな行為だと思います。
別の立場の視点を参照するなら、広告代理店エージェントのジェームズ・ウェブ・ヤングは、『アイデアのつくり方』(今井茂雄訳、CCCメディアハウス、一九八八年)で、「アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と書いています。つまり、新しい組み合わせをつくっていくことがアイデアであると。
ここまでをまとめると、プロジェクトでは、そのプロジェクト固有の言葉が生みだされます。僕たちは、その言葉の辞書的な意味ではなく、文脈的な意味に着目するように心がけています。文脈的な意味というのは、つながり合う関係によって形づくられます。現代美術においては、文脈的な意味がとても複雑に重なっており、その文脈を伝える人が自分なりに観察して解体してみることが重要です。
仲村 今日のタイトルの「サンドイッチ」について考えてみましょう。サンドイッチをどのように食べるのか思い浮かべてみてください。例えば、サンドイッチのトマトを食べて、パンを食べて、レタスを食べてというように口の中でサンドイッチをつくるのか、サンドイッチとして出来上がったものを食べるのかでは果たして同じ味がするでしょうか。同じ素材を口に入れているので、足し算としては一緒ですが確実に何か違いますよね。
つまり、僕たちのスタジオは、たくさん重ねられたサンドイッチの断面のようなアートプロジェクトの一面だけを紹介するのではなく、文脈的な意味の重なりや連なり自体を美しいと思って大事にしています。その関係性にこそ、作品の面白さがあると考えているからです。文脈の複雑さがもつ意味について、建築家の青木淳さんは『フラジャイル・コンセプト』(NTT出版、二〇一八年)で次のように書いています。
ぼくも、できるかぎり「わかりやすい」ものにしたいと思う。わざわざ晦渋にしたり見せたりする必要もない。単純に割り切れるならその方がいい。だけれど、「わかりやすい」か「わかりにくい」かは、建築の善し悪しとはまた別の話だ。建築に求められていることが、最初からはっきりとしているなら、建築は「わかりやすく」なる。言葉と一対一対応する。つまり記号になる。求められていることが流動的で、できあがったあとも未確定な方向に活動が膨らんでいくことが望まれているなら、建築は言葉で割り切れない。記号としては機能しない。つまり、「わかりにくく」なる。ぼくの場合、基本的に明快さを求める方向にありながら、必ずしも明快さの実現が目標になっていない。むしろ、とらえどころなく、膨らみ流動化するその建築の中身と測りあえるだけの論理を持った建築をつくろうと考えていることが多い。
「求められていることが流動的で」というのは、アートプロジェクトでも同じだと思います。それは、建築もアートプロジェクトも人が運営しているから。そのように動き続けているものに対して、断言したり記号をつくったりすることは楽なのですが、そうすると漏れてしまうことや言えないことができてしまいます。
仲村 次に、プロジェクトの言葉を視覚言語に翻訳することについてですが、ここで用いるのが「比喩」です。例えば、「竹を割ったような男」という比喩表現があります。「X(比喩されるもの)=Y(比喩表現)」という数式では、 Xの中には「男」が入り、「Y」には「竹を割ったような」という言葉が入る。日本語話者の皆さんだったら、その男が実際には竹を割っていないことはわかりますよね。ここで大事なのは 「 X = X」 や「 Y = Y」 で表現していないという点です。真面目な人であるということを「竹を割ったような」という別の言葉に言い換えています。そこには、例えを使ったその人なりの見立てみたいなものが発生しています。「竹を割ったような」という言葉には、筋が走っていてパキッと割れる様子や、ちょっと青臭い匂いも含まれている気がします。その人なりの視覚、嗅覚、聴覚、触覚の経験から見立てが発生することが比喩表現の面白いところです。
プロジェクトの言葉という「X」を、グラフィックの「Y」に置き換える時、様々な視覚言語を使って表現することになります。色や文字の形、イラストレーション、写真がそうです。また、印刷物だと、薄い紙にするのか分厚い紙にするのかで、おそらく持った人に与える印象は違ってくるはずです。
一方で、グラフィックによる表現が誤読を誘発することもあり得る。ただ、誤読というのは、見た人の中で「 X」 が「Z」に書き変わっている現象とも言えるので、個人的には面白いとも感じています。誤読は言葉だとなかなか起こらない。その意味通りに受け取りやすい記号だからです。グラフィックデザインは、色合い一つとっても、引きだされる個人の経験や感覚が違います。言語学者のS・I・ハヤカワは、『思考と行動における言語』(大久保忠利訳、岩波書店、一九八五年)で「隠喩、直喩、擬人はもっとも有用な伝達上のくふうで、その素早い感化的な力は、新しい物や新しい感じに対していちいち新しい語を作ることを不要にする」と書いていますが、この「新しい感じ」はアーティストのつくる作品がもたらすものでもあると思います。見たことがないから価値があるわけで、表現するのが難しいのは当たり前。その時にグラフィックによる比喩の力が重要ではないかと思います。
仲村 比喩とは、言葉を通して類推や見立てを行うものですが、その人特有の解釈を含んだメッセージでもあります。そのような個人の解釈が含まれたアーカイブというのは、良いアーカイブと言えるのでしょうか。客観性が大事だと主張するアーキビストからは批判を受けるかもしれません。それに対して僕たちは、客観的でも主観的でもない間主観的な態度をとっています。事実だけを書いているわけでもないし、その人だけの解釈でもない。その人の解釈が他の人にとってもそう思えるような解釈になることを意識しています。事実に対して自分の主観が入っていることが大事だと思っています。
そのために、発信する人と受け取る人の間にデザイナーがいて、最終的には受け取る人が新しく解釈する人になれるようなデザインを心がけています。見る人にきっかけをつくりだす間主観的な解釈により、受け取った人が自分で発見したと思えるようになってほしい。辞書通りの意味を受け取っても、自分の中に面白さは醸成されず、体感として入ってこない。僕たちは、言葉では伝えることが難しい作品の文脈的意味とその重なりの隙間に間主観的な解釈を見つけだし、視覚言語を通して見る人に主体的な解釈のバトンを手渡すことを目指しています。
小林 次に、CHISOUのウェブサイトをどのように考えて制作したかについてお話したいと思います。CHISOUのウェブサイトでは、プログラム情報とレポート記事、それからレクチャーに参加した人の感想が知れる、わかる、残るサイトになっています。このように、バラバラなものをウェブサイトのリンク構造でつなげていく作業が個人的に面白いと思っています。
仲村 CHISOUの特徴だと考えていることは、話す側も何かしらの学びがあり、聞く側も学ぶことがあるというところ。これは、ウェブサイトをつくるにあたって、事務局の皆さんからヒアリングをしている時に感じたことです。今日レクチャーを聞いて思ったことというのはすごく儚くて、数日したら忘れてしまうと思います。それをウェブサイトでどう留めておけるかを考えた時、オフィシャルに残す客観的な文章と、解釈して受け取った受講者の主観的な感想が並列で残ることが面白いと思いました。また、Aさんの感想だけ見ることもできるし、受講者全員の感想を一覧で見ることもできるという具合にしました。
小林 いろいろなコンテンツが紐づくようにしているのですが、つながることの面白さをこのウェブサイトで伝えたかったからです。学ぶことの面白さとは、知識と知識がどんどんつながっていくことだと思うんですね。その知識のつながりみたいなものも見せたいと考えました。例えば、キーワード集を見ると新しい用語が知れる。スタッフによるアートマネージャーのコラムを見ると、アートマネジメントについて深掘りして理解できる。見る人の知的好奇心を誘発することができたらなと思いながらつくりました。
仲村 例えるなら、講義のレジュメとレポートの記事、講義を受けて自分が書いたノート、それからアートマネージャーの先輩が書いてくれる指南書のような虎の巻が並んでいる。情報の質やレイヤーが違うことを有機的に結びつけながら、ひとつのウェブサイトの層をなしているように見せることを、僕たちはやりたかったのです。
今日のレクチャーはこのままだと空間を共有している人だけのものになってしまいますが、レポートとして文字化されるなら、ウェブサイトが残っている限り、地球の裏側から誰かが見るかもしれない。未来に誰かが見るかもしれない。僕たちは発信する人と受け取る人の間で、新しく解釈する人をつくりたいと常々思っています。
仲村 プロジェクトにおいて、僕たちはメッセージを伝えるその人だけが持つ固有の物語や体験を捉え、新しい言葉をつくります。そして、特別さではなく固有性を突きつめることを大事にしています。つまり、「他と比べてすごい」みたいなことではなくて、このプロジェクトでしかできないことは何なのかをいつも考えています。それは、「発信する人」に思いも寄らない疑問符を投げかけることでもあります。CHISOUのウェブサイトをつくる時、お昼休憩を挟んで三時間くらい質問を投げ続けました。僕たちはプログラムや発信する側の外にいる立場だからこそ、受け取る人に近い立場で考えるために気になることを忘れずに聞くようにしています。
そして、プロジェクトの固有の物語や体験を、新しい目線で間主観的に捉え直し、視覚的な比喩表現を通して伝える。「比喩」によってほのめかされることで、見る人は能動的に受け取り、類推を始めます。「どういうことなんだろう」と自ら考え始められるようなコミュニケーションを志しています。類推することで、見る人は新しい解釈を見出していく。物語や体験に新しい文脈や、その文脈から新たな解釈が生まれることで、固定化されずに生き生きと捉え直されるのではないかなと思っています。僕たちはグラフィックデザインを通して、伝える人と受け取る人それぞれが、新たな理解や発見を得ることと、そこから新しい価値を見つけだすことを目指しています。
「グラフィックデザインをサンドイッチのようにつくる」というお話が印象に残った。グラフィックデザインとは不特定多数の人の視覚に訴えるものであり、デザインによっては理解できる人とできない人が出てくる。しかし、あまりわかりやすくしすぎると、今度は伝えたいことが埋もれてしまう。一番の理想は、それぞれの素材はもちろん美味しいが、それらをすべてサンドするとこれ以上ないほど美味しく感じるサンドイッチ。グラフィックのカラーやイラストレーション、印刷物の素材、伝えたいことの物語など、それぞれの要素に重要な情報が詰まっているが、すべてを組み合わせることで最も効果的に言いたいことが伝えられるグラフィックデザインなのだと言う。(石川理香子)
昔・今・未来を旅して、身の回りから地球の裏側にある「ひと・もの・こと」がひとつながりのアートプロジェクトになり、道のり、誰かの思い、見えてくる形と重なって、響き合う。生みだされた層は、誰かの共感や好奇心を刺激しながら厚みを増し、広がっていく。学び得た視点から、これまで自分が実施したプロジェクトをふりかえりつつ、これからの企画について何度も考える機会を得て、講座を受ける前より少しだけ、人に伝える楽しさを感じられるようになった。また、つくっている人と同じ土壌に立って物事を見つめ、対話することは心が安らぐのだと気づいた。そして、その安らぎはまた、誰かの居場所になるのかもしない。気づいたことをそばで教えてくれる人がいることの大切さ、対話を重ねるからこそ見つかる共通言語。「新しい感じを歓迎しよう」と思う。育った環境も、経験してきたことも異なるあなたと、CHISOUを通して知り合えた喜びをサンドイッチにして、一緒に味わえることを願う。(まさきまゆこ)
モノではなくコトを生みだすこと、精神の表現者としてではなくメディエーターとして地域に介入すること。かれらはそれをグラフィックとウェブサイトの分野で、単に格好よいデザインの提示ではなく、カウンセラーのようにクライアントに向き合いつつ、最適な解を見出していくことによって体現している。
昔、藝大の先生が講評会でよく口にしていたことを思い出す。「同じ作品/アイデアを自分が展示したらもっとよい作品になる」。展示経験の少ない学生に対して、見せ方に対して思索や探求が足りないことを指摘しているわけだが、学生を指導する立場になった今、同じことを思うことが多い。藝大は放任主義だったが、県立大にはそもそも芸術を志して入学する学生はほとんどいないために、僕は半分カウンセラーのような形で学生に接している。アートプロジェクトがそもそも作家性を脱構築するものであると考えれば、さまざまな協働によって表現が体現されていくことは、何ら作品性を損なうものではないからだ。
これは学生に限ったことではなくてアートプロジェクトの実際の現場にも当てはまる。つまり、他者と協働することで、同じ作品/アイデアがよりよい作品になるのであれば、アイデアを独り占めせずに、積極的に協働を働きかけるべきだろう。仲村さんと小林さんのカウンセラー的なあり方は、グラフィックやウェブサイトに限らず、アートプロジェクト自体の見せ方の可能性を広げる存在としても心強いものだと感じた。また、おそらく一度そのように協働すると、別のプロジェクトでお二人と一緒にならなかったとしても(あるいは今回のようなレクチャーを受けるだけでも)、仲村さんと小林さんならこんな疑問を投げかけてくるかもしれないと、お二人の視点のわずかでも内面化することができそうだと感じる点で、お二人は協働を通して、学び合いの場もまた実現している。