REPORTS
乾聰一郎「図書館という場を編み直す──関係のないものを編集でつなぐ」
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
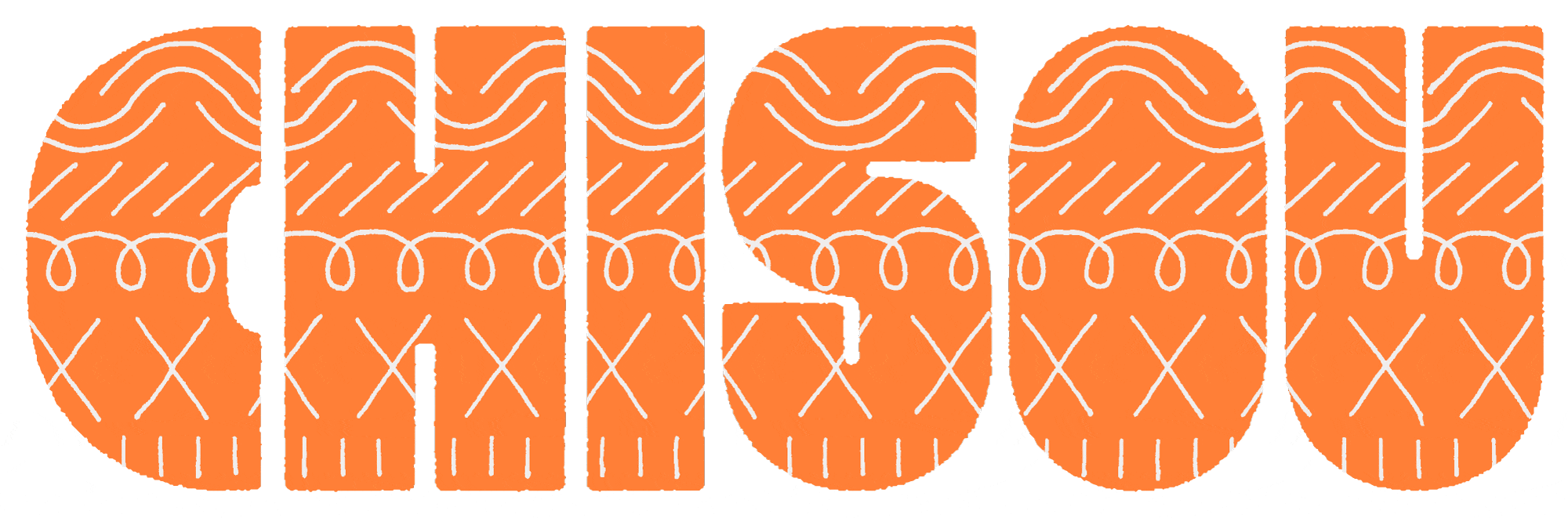
REPORTS
奈良県立大学 CHISOU lab.(オンライン配信あり)
共有編の最終回は、奈良県立図書情報館で開館以来、運営や企画に携わってきた乾聰一郎さんをお招きし、まちの記憶装置の要である図書館が地域の中で担う役割の変遷を辿りながら、古今東西の情報・人・場を創造的につなぐ編集と発信のマネジメントのあり方について探りました。
CONTENTS
図書館は本を読んだり、勉強や調査、研究をしたりするところだと思われがちです。実は私は図書館の専門家ではなく、たまたま図書情報館の建設準備室に入ることになり、開館まで六年間準備室で、そのまま開館以降ずっと働いてきました。計画では様々なコンセプトを考えましたが、実際に開館してみると、勉強や調査、研究をする場所だったり、居場所だったり、ある意味とても日本的なコンセプトで施設が成り立っているなと感じています。
図書館に対するそのようなイメージは、これまで大多数の人がもってきたのに加え、コロナ禍によりさらに明らかになりました。やはり図書館は本を借りにいくところで、それ以上でもそれ以下でもない存在だった。別にネガティブに言っているのではなく、「本があってよかった」という話はあったけれど、それは図書館でも書店でもよかった。当館も三ヶ月ほど休館しましたが、休館明けは拍子抜けするくらい人が来なかった。今回のコロナ禍を受けて、図書館は一体どんな存在だったのかについて振り返る機会になりました。
図書館を使っている人の数は、全体からみると少数です。大多数の人にとっては、生活の中に図書館はなくても困らない。たまに図書館が大好きな人が少数いまして、そういう方は非常に関心をもってくださいますが、図書館に関心がない多くの人にとっては、図書館はないに等しい。図書館に限らず、美術館でも博物館でも何であっても、関心がない人にとっては存在しないのと同じです。そういうふうに認めてしまった方がよいと僕はずっと考えてきました。そういう人が多いのであればこそ、そこに図書館のこれからの鍵があると考えています。つまり、「パイは補集合に存在する」と考えることができる。
このプログラムの受講者には奈良でアクションを起こそうと考えている人も多いと思いますが、マーケティングしてニーズに応えようと思っている方が多いかもしれません。でも、ニーズに応えたら消費されて終わってしまうだけ。むしろ、ニーズはつくりだす方がいい。そのためには自分のアンテナや感性を総動員して何かを投げかけないと、関心をもってもらえない。ニーズをつくりだすのは非常に難しく、自分自身が問われることになります。
僕は図書館で働いているので、そこに図書館という場を編み直すための一つの要素があるのではと考えてきました。ニーズをつくりだす、つまり知的好奇心を呼び起こすためにはどんな仕掛けをしていくのかをいろいろ考えてきました。手っ取り早いのは、図書館に来ると何かの役に立つとか、課題の解決になると謳うこと。図書館は無料の貸本屋だと、だいぶ叩かれた時期がありましたが、ちょうどその頃に『未来をつくる図書館—ニューヨークからの報告』(菅谷明子、岩波新書、二〇〇三年)が出版されるなど、ニューヨーク公共図書館が日本で話題になりました。ニューヨークの公共図書館に通っていた人が何かを発明して特許を取り、アメリカンドリームを実現したような話です。パッとそこに乗っかって出てきたアイデアは、「課題解決ができる」とか「ビジネスの役に立つ」というもの。でも、気をつけなければいけないのは、役に立つことは存在意義があるけど、役に立たないことは存在意義がないという単純な思考に陥ってしまうことで、知のアーカイブをする施設としては致命的です。本を選んで後世に伝えるためにはどうしても取捨選択をしなければなりませんが、その時にこの基準では困りますよね。
皆がいろいろなものを出しあって共有したり共感したりする場でないと、公の施設としてはダメじゃないかと考えてきました。そういう場になるためには、「どんな場でもあり、どんな場でもない」必要があるのではないでしょうか。図書館に限らず、生活の中にはそういう場がなかなかない。それが図書館と非常に親和性があると思っています。分野を問わず本や情報が山のようにあるという土台があります。それに対してコンサートホールは基本的に箱しかなくて、そこにオーケストラが来ないとコンサートは成立しません。でも図書館は箱でもあるけどリソースが山のようにあって、しかも無料です。そして重要なのが、目的があってもなくてもよいということ。単なる居場所であってもよいし、目的がなくても訪れてよい。
それと、スペースがいっぱいある。ひと休みしたり、ちょっとした空間が展示スペースになったりなど、マルジナリア(「余白」の意)とでもいうような空間が随所にあって、フレキシブルな使い方ができる場かなと考えています。図書館は本を買わなければならないのでお金はかかりますが、皆に利用してもらっても収益は生まれない。これは運営する側には致命的に不利なことですが、収益の代わりに生まれるものが何かについて説得的に言えたらいいなとずっと考えてきました。
公共図書館の「公共」とは何かということについても、ずっと考えてきました。利用する個人の方に対して、図書館はサービスを提供している。行政が公共を担っており、個人はそのサービスを受けている。でもよく考えたら、この公共と個人の関係だと、公共はサービスを提供して個人はサービスを受けるだけなので、「こうしてほしい」とか「けしからん」という関係にしかならない。個人からは要望とクレームしか出てこない。だから公と共を切り離して、公と個の間に共があるべきだと考えてきました。
僕は、公と個の間にあるものを「共生空間」と呼んでみたいと思っています。そこでは、公がサービスを提供するだけではなく、個人も働きかけて、お互いにフォローしたりされたりする関係がある。行政が市民グループと一緒に図書館をつくったりする事例のように、図書館にはそういうパターンが結構あると思われる方もいるのではないでしょうか。これは全く悪いことではないですが、コミュニティは少数のグループで上手くいってしまうと、そのコミュニティがすべての代弁をしてしまうイメージになってしまう。一時期、コミュニティ・デザインということがもてはやされましたが、コミュニティは基本的に閉じてしまうということに注意する必要があります。そこが非常に難しいところなんです。最初に「パイは補集合にある」と言いましたが、協働するグループには含まれない大多数の人たちがどのように関わればいいのか、どうしたら関わるきっかけができるのか。そのような実験をするには、図書館はもってこいかなと思います。
そのためには、そこに行くと開かざるを得ないという空間づくりが必要です。「コモンズ」という概念がポイントでして、皆で共有するための、他者のための場づくりというイメージです。自分がやっていることは、自分の利益ではなくて、実は他者のためで、それが全体としての利益につながっていく。そんなことを図書館で実験するのは非常に面白いと思います。だから共生空間は緩くなければなりません。ゆっくり長くやっていく場づくりをずっと考えながら、僕はいろいろと試みてきました。
新型コロナウイルスの感染拡大によって図書館が休館した時、「場としてのリアルな図書館の試みは不可能になった」と言う図書館の専門家がいたのですが、場としての図書館という時の「場」の捉え方が一面的だと感じました。場や空間というのは、リアルであろうがバーチャルであろうが、何によって成立しているかというと、共有や共感、共生であると僕は考えています。そのための手段としてリアルにイベントで交流するのもありですが、せっかくこういう状況になってしまったのなら、ICTやいろいろなメディアを駆使して、新しいつながりを育む空間や場をつくればいいじゃないかと。僕は図書館そのものがメディアだと思っています。物理的に近接していなくても、気持ちは近接している。それをどのようにつくりだしていくかは、新しい課題でも何でもないはずです。
二〇〇六〜〇九年に「自分の仕事を考える3日間」というフォーラムを開催したのですが、二〇一五年にも番外編を開催しました。そこでは様々な分野の人が集まって自由に話をしながら数日間を共に過ごしました。こんな生き方もある、こんな考え方もあるということを、皆で共有したり共感したりする。館としては最低限フォローできるところはしましたが、参加する人たちが皆であの空間をつくっている。だいたい一日あたり三百人くらい来ましたので、新型コロナウイルスの今だと非難轟々の密な状態でしたが、例えば今の技術でなんとかできないだろうかと考えることはできますよね。もしかしたらお互いが働きかけることによって、リアルではないけど、何か場や空間ができるということはあり得る。そんなふうにこれから奈良でアクションを起こす方がいたら面白いなと思っています。また、これらのフォーラムをもとに『自分の仕事を考える3日間 Ⅰ』、『みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの? 自分の仕事を考える3日間 Ⅱ』、『わたしのはたらき— 自分の仕事を考える3日間 Ⅲ』(西村佳哲with 奈良県立図書情報館、弘文堂、二〇〇九年、二〇一〇年、二〇一一年)に書籍化されていますので、関心のある方はお読みください。
ちょうど一時間くらいお話をさせていただきましたが、ここからは皆さんからの質問に答えるかたちでお話を進めていけたらと思います。
──緩くゆっくり長く場づくりをしていくとなると、私だと思いつめたり、必要以上に自分にプレッシャーをかけたりしてしまうことが多くなります。緩くゆっくり長くのコツを教えてもらえますか。
自分が主導していると、自分で何もかもしなければと思ってしまいます。けれど、いったん全部を吐きだして、皆で共有して、その課題に対して「こんな方法もある」というアイデアがあちこちから出てきて、全く関係のないものが結びついて化学変化が起こるような環境づくりが必要だと思います。人が多ければ多いほど解になる可能性のあるものが多く出てくる。自分がメインから一歩外れて「何かいい案はないかな」と皆で考えるのが一つの方法ですね。緩いというのは、本当に自分が緩くないとできません。あまり真面目すぎるのはいけないかもしれませんね。即効性を生む必要もないし、何か利益を生む必要もないし、役に立つか立たないかもどっちでもいい、そんな感じを貫いていたら、自然と緩くなります。その根っこにあるのは、「楽しいから」という気持ちに尽きるという気がします。
──乾さんにとって、公と個をつなぎながら緩くゆっくり長く取り組みをしている図書館が他にありましたら教えていただきたいです。
あまりないですよね……例えば、九州の伊万里市民図書館のように、コミュニティと行政が一緒に図書館をつくろうという取り組みはあちこちにあります。でも、なかなか長く続けるのが難しい。お互いにタッチしすぎると、行政側の担当者が代わって終わりとか、市民側も代替わりして終わりということが往々にしてある。緩くゆっくりはできても、長くというのがなかなか大変です。ある程度は放ったらかしにしていることが大事かもしれない。放ったらかしにされているから向こうは勝手にやっている。でも、たまには「どうしてる?」みたいな感じ。そういうつながりはなかなか難しいですけど、続けていくためにはそれぐらい緩くないと難しいのではと思います。
実は奈良県立図書情報館では、開館の三年前頃からずっと続いているITサポーターの活動があります。館の情報機器を駆使して勝手にいろいろなものを発信してもらおうという趣旨でした。現在は平均年齢が七十歳くらいですが、大手電機メーカーをリタイアした直後の方々が集まってきて、かれらは元サラリーマンだから最初は指示を求めてきたのですが、今では指示されるのを諦めて自分たちで勝手にいろいろなことをしています。例えば、奈良の今昔写真を探しだしてきてウェブで全部アップしているのですが、テレビ局や新聞社、出版社から使わせてほしいという引きがすごくある。皆さん調子にのってコンテンツがどんどん増えていく。最初は個人が所有する写真を発掘していましたが、そのうち企業が持っていることがわかり、勝手に企業に問い合わせて、「館からちょっと文書を書いて」みたいに言う。何の利益もないですが、皆さんすごく楽しそうに続けている。毎年自分たちで企画展をするのですが、それも自分たちでミーティングして自分たちでやる。会場で知り合った人が、サポーターに加わってくるという感じで、いつの間にか十五年間も続いています。
そんなふうに長く続けるというのは本当に大変で、どちらも忍耐が要ります。さらに開きっぱなしにしておくというのは、すごくエネルギーを使います。閉じている方がやりやすい。室内の温度を保ちながら窓や扉を全開にするのと同じで、熱量を維持するためには閉じた方がよい。でも、そうすると一酸化炭素中毒になるので、そうならないように開きながら熱量を維持するというのは、すごく難しいですね。
──「長く続ける」という時の「長く」という時間軸は、一体どれくらいなのでしょうか。ご高齢だとお亡くなりになったり、どうしても世代交代があったりします。場合によっては、長さについての捉え方も変える必要があるかもしれませんね。
僕が基準とする時間軸は「続けることが目的になればやめたらいい」という考えです。例えば「自分の仕事を考える」というフォーラムから、ビブリオバトルを運営するグループが生まれました。これも館が集めようとしたのではなく、自分たちも何かやりたいと若者たちが集まってきた。運営もすべて自分たちでやって、チラシも自分たちでつくる。メンバーにはデザイナーや写真家もいて、自分たちのスキルを活かして、勝手に部誌をつくったり、自主講習会やイベント、展示をしたりしていました。
二〇一一年三月に一回目のビブリオバトルが開かれて、そこから五十回は続くかなとなって、五十回になり、昨年三月に百回目を迎えました。メンバーそれぞれが学校を卒業したり、立場も変わったり、達成感もあったりして、今のところ消滅した状態になっています。そうやって自然になくなることもあるし、もし続けるのが目的になったのなら続けない方がいいかなと思っています。「自分の仕事を考える3日間」というフォーラムも三年でやめました。「どうしてあれほど人がたくさん来るのにやめるのか」と言われましたが、人を集めて続けることが目的になりそうでしたのでやめたのです。
──図書館という言葉をアートプロジェクトに置きかえても共通することばかりだなと思いながらお話を伺っていました。様々な活動の成果は、何をもってどのように判断や評価をなさっているのでしょうか。
アーカイブをして、それを共有できるという手段があれば、評価は必要ないと考えています。先ほどニーズをつくりだすという話をしましたが、ニーズをつくりだすのはあくまでも自分たちの感性や考え方、こうしたいという思いです。だから、そこを評価することはないかなと思う。それをすると、評価軸は何かという話になり、イベントの集客数やテレビの視聴率のように数量化されてしまう。しかし、面白いと手をあげる人の割合が多ければそれでよいのかどうか。本についても同様で、皆が借りるから良い本とは限らないし、ベストセラーを集めたらよいのかということと同じではないかと思います。ただアーカイブを共有できる場があることが大事だなという気がします。いつでも取り出して共有できる「場」というか、それはまさしく図書館という「場」でもあるんだと思います。
収益を生まない活動やアートプロジェクトみたいなものは、そもそも定量化や数量化に親和性のない事柄なんだと開き直る必要がある。そこに評価軸を据えてしまうと、その数を稼ぐための芸術活動になってしまって、本末転倒どころか全くちんぷんかんぷんなことになるのではないでしょうか。収益を上げなくてもよいという前提があってこそ、経済原則によらない場があってこそ、アートを含む文化活動が総体として後世に伝わる大きな知になっていくのかなという気がします。
奈良県立図書情報館は、「奈良県立図書館」ではない。書籍はもちろん、最新のパソコンで調べることもできる。また会議室や撮影スタジオ、画像編集ソフトなど、自分たちで情報を集め、まとめた情報を発信する環境が整っている。図書館主催のイベントや、利用者と共同で企画したイベントも多数開催されている。また利用者が立ち上げ、運営するプロジェクトも数多く生まれて、利益を追求しないからこそできる画期的で魅力的なイベントが多数開催されている。「図書館は本を借りる場所」という概念が覆される。こんなに情報収集や発信のできる施設が、無料、または少しの金額で使えることにとても驚き、ぜひ調べものをする際に利用したり興味のあるレクチャーの際には参加したりしてみたいと思った。(石川理香子)
まるで本を読み進めていくように、鍵となる言葉が、ひとつ、またひとつ、とあらわれる。「Alter-native Complement Commons」。私の暮らす小さなまちに、「コモンズ」という名のスーパーがある。老若男女、日常生活で耳慣れている言葉に物語が加わる。講座の前夜、海外の画家が「ドローイングはreflectionであるから、心が波立っていると何も映しとることはできない。風のない静かな湖面だからこそ鏡のように対象を映しだすことができる」と、芭蕉の俳句を通して気づいたことを話してくれた。映しだすには光も必要だと思う。関わり合う人、楽しい気持ちの中に、私は光を見る。ひとつひとつの言葉が、ある点に積み重なり、重なりからまた学ぶ。言葉は事象にもなり得る。文化や歴史を伝える。親しまれてきた記号。緩やかに、心地よく。編んでは解いての繰り返し。間をおいて。よく見つめて。耳を傾けて。(まさきまゆこ)
奈良県立図書情報館は、「奈良県立図書館」ではない。書籍はもちろん、最新のパソコンで調べることもできる。また会議室や撮影スタジオ、画像編集ソフトなど、自分たちで情報を集め、まとめた情報を発信する環境が整っている。図書館主催のイベントや、利用者と共同で企画したイベントも多数開催されている。また利用者が立ち上げ、運営するプロジェクトも数多く生まれて、利益を追求しないからこそできる画期的で魅力的なイベントが多数開催されている。「図書館は本を借りる場所」という概念が覆される。こんなに情報収集や発信のできる施設が、無料、または少しの金額で使えることにとても驚き、ぜひ調べものをする際に利用したり興味のあるレクチャーの際には参加したりしてみたいと思った。(石川理香子)
まるで本を読み進めていくように、鍵となる言葉が、ひとつ、またひとつ、とあらわれる。「Alter-native Complement Commons」。私の暮らす小さなまちに、「コモンズ」という名のスーパーがある。老若男女、日常生活で耳慣れている言葉に物語が加わる。講座の前夜、海外の画家が「ドローイングはreflectionであるから、心が波立っていると何も映しとることはできない。風のない静かな湖面だからこそ鏡のように対象を映しだすことができる」と、芭蕉の俳句を通して気づいたことを話してくれた。映しだすには光も必要だと思う。関わり合う人、楽しい気持ちの中に、私は光を見る。ひとつひとつの言葉が、ある点に積み重なり、重なりからまた学ぶ。言葉は事象にもなり得る。文化や歴史を伝える。親しまれてきた記号。緩やかに、心地よく。編んでは解いての繰り返し。間をおいて。よく見つめて。耳を傾けて。(まさきまゆこ)
図書館が「無料の貸し本屋」という認識にとどまっている限り、図書館と利用者にはサービスの提供側とそれを促すニーズ(要求あるいはクレーム)という以上の関係性が生まれない。パイは補集合にあると考える乾さんは、図書館を舞台に新たなニーズをつくりだす活動を様々に実践してきた。その中心になる考えが、図書館と利用者の関係を「公共と個人」から、「公、共、個人」へと解体するというものだ。「公共」と「個人」が直接向き合う関係ではなく、「公」と「個人」が互いに向き合う先としてある「共」のことを、乾さんは「共生空間」と名づける。これは、小山田徹さんが用いる「共有空間」という概念と同義と考えてよいのではないだろうか。小山田さんが例えば焚き火の場をつくるように、乾さんもこうした空間は「ゆるく、ゆっくり、長く」がよいと言う。
アートプロジェクトやそのアーカイブを考える立場として、乾さんの言葉はじわじわと響いてくる。曰く、「役立つことはすぐに役に立たなくなる」「続けることが目的になったらやめたらいい」「人々の活動の動機は感性的なものなので、これに評価はいらない(アーカイブして共有できるものにさえしておけばよい)」のだ。
レクチャーで紹介された「自分の仕事を考える3 日間」。実は初めて開催された2009年の1月、たまたま東京から帰省していた僕も参加していた。こんな企画が、こんな図書館が、奈良にあるのか。会場の熱気と、グループワークで初対面の人と語り合った興奮を今でも身体が覚えている。そうして僕もまた、図書館でのあの出来事を思い出し、奈良でアクションを起こしている一人なのだ。乾さんが当時試みた共生空間の実験を、僕の身体がアーカイブしている。