REPORTS
- レクチャー
「音から読み解く『万葉集』と明日香村」
井上さやか
2021年8月1日(日) 13:00–16:00
奈良県立万葉文化館
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
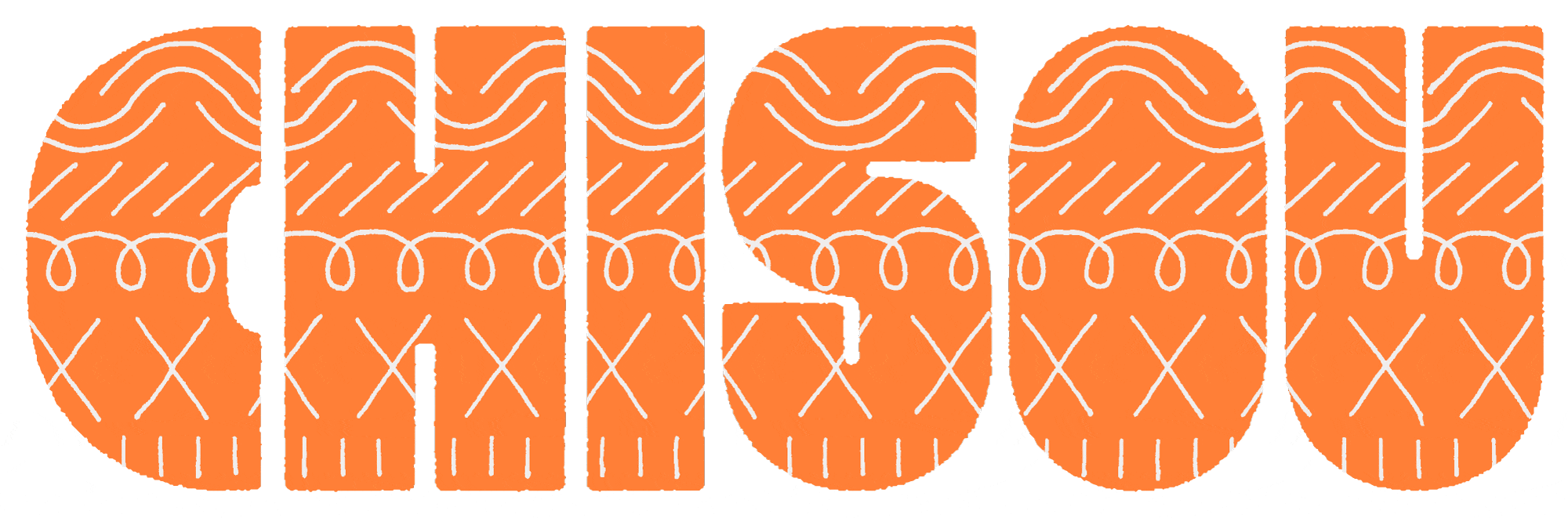
REPORTS
2021年8月1日(日) 13:00–16:00
奈良県立万葉文化館
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

『万葉集』の研究者である井上さやかさんによる案内のもと、奈良県立万葉文化館の展示室を鑑賞した後、『万葉集』の歌を手がかりに明日香村の歴史とサウンドスケープについて学ぶレクチャーを実施しました。これから明日香村でフィールドリサーチやプロジェクトの制作を進めていくにあたり、「当時の日本の人々は音を通して世界をどのように捉えていたのか」を想像するための糸口を掴むことができました。
CONTENTS
『万葉集』の歌は、もともとは文字で書かれたものではなく、声に出して歌うものでした。そのような歌を後から文字で書いて残したのが『万葉集』です。現存する最古の歌集ですが、『万葉集』には今は残っていない歌集名がいくつか出てくるため、『万葉集』より以前に文字として書かれた歌集があったことがわかります。
平仮名やカタカナがない時代の書物でしたので、外国語の文字であった漢字で全て書かれました。全く言語体系の異なる中国語のためにつくられた漢字で、当時の大和言葉を表そうとしたのです。音声言語であった日本語を漢字で書く時に、様々な工夫をしていたことについて、五つの歌を例に挙げながら解説しましょう。

「寒」と書いて「ふゆ」、「暖」と書いて「はる」とよみます。寒い季節や暖かい季節という意味をそのまま当てたのでしょう。「冬過ぎて 春来るらし 朝日さす 春日の山に 霞たなびく」とよみますが、漢字だけで書かれていると、よみ方もわからないし、歌かどうかさえわからない。幸い短歌ですから、五七五七七の31音というのがヒントになり、そのリズムに合わせて読んでいくことになります。
「冬が終わって春が来たらしいよ、朝日の差す春日山で、霞がたなびいているから」という意味でして、季節の移り変わりを詠んでいる。朝日の「日」を表す字が「烏」と書かれている。太陽神のお遣いとして烏がいて、月神のお遣いとして蛙がいるという発想が中国から日本にやってきて、当時の政権にも浸透していました。「日」という字を書かず、あえて太陽神のお遣いである「烏」と書くところが、ちょっと洒落ていて工夫を感じます。
「春日」と書いて「かすが」とよむのは、「飛鳥」と書いて「あすか」とよむように、独特な歌のきまり文句として定着しているからこその書き方です。また「滓」と「鹿」という字を組み合わせて「滓鹿」と読ませています。発音だけが重視されており、漢字の意味として良いか悪いかはあまり重視されていなかったようです。「来るらし」も「来良思」と書かれていますが、漢字の意味は関係なく、「良」は「ら」という発音として、「思」も「し」という発音として、「らし」という日本語の助動詞を表現するために、漢字を平仮名のように使っていました。
このように1字1音に対応しているものが用例として最も多かったのが『万葉集』だったので、万葉仮名と呼ばれていますが、木簡にも使われたり、『古事記』や『日本書紀』の歌の部分にも用いられたりしました。平仮名やカタカナと同じように、1字1音でないものは万葉仮名とは言いませんので、『万葉集』は全て万葉仮名で書かれているというのは正しくありません。
「二八十一」もクイズみたいな書き方ですが、漢数字の「二」はそのまま「に」とよみ、「八十一」は「9×9=81」なので「くく」とよむ。当時から掛け算の九九はあって、山田寺の瓦にもヘラで書かれた掛け算九九の跡がある。建築関係など計算が必要な職業があり、ガラス玉や富本銭などをつくっていた技術者は大陸から亡命してきた人々だったようですので、技術と一緒に数学的な発想も入ってきたのでしょう。
この歌は新婚初夜を詠んだ歌でして、当時は一夫多妻制で複数の人と結婚することもあり別居婚が一般的だったようで、「新婚の最初の日に手枕を初めて枕いて、これから夜を隔ててしばらく通ってこないということはないよ、あなたのことが好きだから」という意味です。
これは長歌の一部です。今でこそ和歌と言うと短歌ばかりで、五七五七七で一つの歌というのが一般的ですが、古代の歌には五七五七五七……と続く長い歌も多く、五七を何回も繰り返すことで長い歌が簡単にできる。そのようにつくられたのがこの歌で、五七五七の途中を抜き出したものになります。
『万葉集』には浦島太郎の話も長歌として載っていますが、五七五七五七というリズムでずっと語られていく。現代だと物語と和歌は明確に分けられていますが、古代の人々は歴史を語る時もリズムに乗せて暗唱していた。文字がない時代からずっと語られてきたので、記憶術の一つとしてリズムをつけた言葉が用いられていたのでしょう。枕詞など特有の表現技法はその名残だと言われています。
古い歌で一般的だった五七五七五七五七というリズムでは、意味の切れ目が二句ずつであることが多いので五七調と言われます。平安時代になると、長歌が廃れて短歌ばかりになり、五七五で意味のまとまりができることが多くなります。現代のかるたや百人一首でも、五七五が読み札で、最後の七七だけが取り札になっている場合が多いですが、『万葉集』の歌をかるたにすると、非常に意味が取りにくくなったり、途中で途切れているような気がしたりして、古代の歌のリズムが平安時代以降の七五調とは異なることがわかります。
この歌は「見るごとに 恋はまされど 色にいでば 人知りぬべみ」とよみますが、「山上復有山」は「山上にまた山有り」という漢文です。山という字を書いて、その上にもう一つ山という字を重ねて書くと、「出」という漢字に見える。「色に出でば」とは「そぶりに出す」という意味ですが、クイズみたいですね。「出」の字は簡単なので知っているはずですが、あえて「山上復有山」と五文字も使って書くのは、明らかに遊んでいる。このような表記の仕方を古代の人は面白がっていたようで、歌の意味だけを鑑賞していくと『万葉集』の面白さを取りこぼしてしまう気がします。

「かくしてや なほやまもらむ 大荒木の 浮田の社の 標にあらなくに」とよみますが、「このようにして、いつまでも守っていくのだろうか、私は大荒木の浮田の社の標ではないのに」という恋の歌でして、「相手を守ってあげても何の利益もない」と嘆いているようです。
「牛鳴」は、オノマトペである牛の鳴き声を転写した言葉になります。当時の人は牛の鳴き声をどのように聞いていたのでしょう。現代では牛の鳴き声は「モーモー」と聞こえますが、古代の人は「ムームー」と聞いていたらしい。なので、この2文字「牛鳴」で「む」とよませています。「なほやまもらむ」の助動詞「む」の音を「牛鳴」で表すという非常に面白い例です。
「たらちねの 母がかふ蚕の まよごもり いぶせくもあるか 妹にあはずして」とよみ、眉毛の「眉」という字で書かれていますが、意味としては絹糸をとる「繭」を表しています。このような当て字が『万葉集』ではたくさん用いられています。「蚕が繭にこもっているように、心がこもってうっとうしい」ということを意味しています。
「馬声蜂音」という文字ですが、2文字ずつ分けて、馬の鳴き声をどのように聞いていたのかを考えてみましょう。現代だと「ヒヒーン」というのが一般的ですが、古代の人は「イイーン」と聞いていたらしい。そのため「馬声」と書いて「い」を表します。一方の蜂は「ぶぶぶぶぶぶ」と飛んでいると当時の人は感じていたようで、「蜂音」と書いて「ぶ」を表します。
ということで、「馬声蜂音石花蜘蛛荒鹿」は「いぶせくもあるか」と読みます。「いぶせく」というのが「心がこもってうっとうしい」ことを表す言葉です。「くも」は昆虫の蜘蛛という字を当てている。本当に当て字のオンパレードでして、現代の国語が得意な人ほど逆に読めないのではないかと思うくらい、変な使い方をいっぱいしています。

奈良時代になっても、このような表記方法は色々と使われているのですが、平安時代になると平仮名やカタカナができて、『万葉集』は読めなくなっていく。千年以上にわたって歌集としての研究資料が蓄積されているのですが、いまだに読めていない歌も存在しています。
初期の飛鳥の万葉歌をご紹介しようと思いますが、前提として飛鳥に都があったことをご承知おきください。平城京や平安京のような碁盤の目状の街並みの都ではなく、もっと古い形の都です。西安や長安など中国の都は、外敵から守るために街を全て高い塀で囲っていましたが、日本だと門はあっても横の塀は途中で途切れている。中国風の都城を真似て、碁盤の目状の街並みをつくりながら、それを全て囲う長大な壁はつくらないというように、中国文化をアレンジした形で取り入れています。もともと「都」の字は、塀で囲われた中国の街並みをイメージするのですが、日本に輸入された時には「宮がある場所」という意味で「みやこ」という発音がその字に当てられた。
日本には春になると芽が膨らんで植物が膨張していくという意味の「はる」という言葉があり、その言葉が中国の「春」の字と融合していきました。そのように、中国の発音を日本風にした音読みと、日本語本来の語源を持つ訓読みの両方が日本語にはあり、複雑になるとともに、色々な表現が可能になってきました。
国の史跡である「飛鳥京跡」はかつては「伝飛鳥板蓋宮跡」と呼ばれていましたが、発掘調査で少なくとも三期にわたる宮の跡が重層的にあるということがわかり、名称が変更されました。舒明天皇の飛鳥岡本宮、皇極天皇の飛鳥板蓋宮、斉明天皇と天智天皇の後飛鳥岡本宮、そして天武天皇と持統天皇の飛鳥浄御原宮、少なくとも70年間に及ぶ歴代の天皇の宮跡が同じ場所から発見されたため、現在は「飛鳥京跡」と呼んでいます。
「飛鳥」と書くようになったのは、実際に鳥が飛んでいるからというより、概念として、鳥がたくさん飛ぶような場所には、鳥の餌になる生き物がたくさん棲んでいて、土地が豊かであることを象徴していたからではと考えられます。現在は「明日香村」と書きますが、万葉文化館がある辺りは大字名として「飛鳥」が残っている。『万葉集』では、「明日香」と書かれているものが一番多いですが、他にも「飛鳥」と書かれていたり、万葉仮名で「阿須可」とか「安須可」とか色々な当て字で書かれていたりします。飛鳥京跡からは「飛鳥寺」と書かれた最古の木簡が出土しており、少なくとも7世紀後半には歌の文句として定着した「とぶとりのあすか」に基づき「飛鳥」という書き方が用いられていたことがわかります。
サウンドスケープという観点から選んだ歌について紹介します。例えば、雪が降る音は、無音だと言うべきなのかもしれませんが、やはり気配を感じます。「我が里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくは後」という歌がありますが、「我が里」は、天武天皇が住んでいた飛鳥浄御原宮だと考えられます。当時、雪は天からの祝福だと考えられ、豊作を約束するものだったため、都に大雪が降ったことを天皇が自慢している歌です。しかも「あなたが住む、大原の古びた里に降るのはずっと後でしょう」と相手をからかっている。それに対して藤原夫人は、「何を言っているのですか、私の里の丘に棲む水の神に命令して降らせた雪のおこぼれが、あなたのところに降ったに過ぎない。本当に祝福されているのは私のところですよ」という歌を天皇に返しました。よほど親しい間柄でないと詠めないような歌ですね。
この藤原五百重という人が住んでいた大原の里は、今は「小原」と書きますが、藤原鎌足が生まれた場所だと伝わる藤原神社が残っている。鎌足が使ったと伝えられている井戸の跡もありますので、ぜひ秋のフィールドリサーチで訪れてください。飛鳥坐神社のすぐ近くです。
また、「大口の 真神が原に 降る雪は いたくな降りそ 家もあらなくに」という歌にあるように、当館の辺りは「大口の真神が原」と呼ばれていました。「大口の」は枕詞で、「真神」は狼のことです。かつてはこの辺りに狼が生息していたらしい。「大きな口を持っている狼が住んでいるこの真神が原に雪が降っている。どうか激しく降ってくれるなよ、ここに家もないのだから」というような意味でして、女性が、雪が激しくなるのを見て、訪ねてきた恋人が帰っていくのを心配している歌です。
当時も飛鳥川が流れていたので、水の流れについて頻繁に詠まれています。例えば、「明日香川 瀬々に玉藻は 生ひたれど しがらみあれば 靡きあはなくに」という歌の「玉藻」は藻ですが、水草に対する褒め言葉が「玉」でして、「玉のような赤ちゃん」という時と同じ意味ですね。その藻が激しい川の流れで揺れて絡み合うように、私たちも互いに靡き合っていきたいが、しがらみがあるので靡き合えない、というような恋の歌です。
「ふさ手折り 多武の山霧 繁みかも 細川の瀬に 波の騒ける」には、石舞台古墳の奥にある細川が詠まれています。「多武峰に深く立ちこめた霧が濃いためか、細川の瀬の波音が激しく聞こえる」という意味で、川の流れの清らかさや激しさを表現しています。「明日香川 明日も渡らむ 石橋の 遠き心は 思ほえぬかも」も川の流れをイメージさせる歌で、背景に水の音がする気がします。「明日香川の名前の通り明日も渡ろう。川の流れの中に置いてある飛び石のように、自分の心は離れていないよ」という恋の歌です。
「釆女の 袖吹きかへす 明日香風 みやこを遠み いたづらに吹く」は、飛鳥から藤原に都が移った後に詠まれた歌として有名です。采女とは天皇にお仕えした才色兼備の女性のことで、身分がそれなりに高く、教養もある美しい女性だけがなれる特別な役職です。その煌びやかな衣装の袖を翻す風を詠んでおり、高貴な人々が集う都のイメージを彷彿させますが、今はもう飛鳥には都がなく、誰もおらず、ただ風だけが虚しく吹いている、という隔世の感を表現した歌です。
飛鳥から藤原京まで実際はそれほど離れていませんが、都の在り方や仕組みが大きく変わったのがこの時期でした。飛鳥の時代の街並みは中国風の碁盤の目状ではなく、衣装も韓国風でしたが、藤原京では中国風の衣装になっていった。時代の移り変わりが象徴的に詠まれています。
飛鳥では漏刻と呼ばれる水時計が初めてつくられました。水時計は水音と水位によって時の移り変わりを計ることができます。これも中国から渡ってきた技術ですが、人々に時報として鐘や鼓で時を伝えていました。「皆人を 寝よとの鐘は 打つなれど 君をし思へば 寝ねかてぬかも」には、時を伝える鐘の音が表されていますし、「時守が 打ち鳴す鼓 数みみれば 時にはなりぬ 逢はなくもあやし」の歌からは、鼓の音が時報を担っていたことがわかります。
奈良時代以降、飛鳥を懐古した歌が盛んに詠まれるようになり、鳥の鳴き声などがよく出てきます。「わが背子が 古家の里の 明日香には 千鳥鳴くなり 島待ちかねて」は、長屋王が謀反の罪で亡くなる以前に飛鳥を想って詠んだ歌です。「島」は人工の庭園を意味しました。天皇だけが持つ人工の庭園を、蘇我馬子も持っていたので、「島の大臣」と呼ばれていました。現在も島庄という地名が残っていますが、その島を待ちかねて千鳥が鳴くという表現が出てきます。
他にも川の水音や鶴の鳴き声と羽ばたき、蛙の鳴き声など、それらの音を通して飛鳥の古き都を懐かしく思ったり嘆き悲しんだりする歌が、奈良時代には詠まれています。春雨が降って激しくなった瀬の音を聴きたい、と詠んだ歌もあります。
当時は音と声をそれほど厳密に使い分けていませんでした。「音」という字で「おと」や「こえ」、「ね」という大和言葉を当てますが、「おと」という読み方にも「音」と「声」の両方の漢字を当てはめていた。「春風の声」と書いて「声」を「おと」と読ませたり、「ホトトギス 鳴くなる声の 音の遥けさ」では「声」と「音」とを重ねていたりする。現代とは違う感覚で音と声とを捉えていたように思います。動物と人間をそれほど明確に分けておらず、自然の音が非常に身近にあった時代に詠まれた歌が『万葉集』に残されているのです。
『万葉集』の歌から、人の心と自然が一体化していたことを知った。自然の音(または声)、景色、香りなどを、歌人たちは恋や趣、安らかさ、悲しさなど、自分の心と一体化させ、歌に詠んでいたことが感じ取れた。人間は自然の中で生き、他の動物と同じように自然を感じ、自分と照らし合せることで自然と向き合うことが大切だ。今も昔も同じ人間なのだから、昔の人がしてきたことを私たちができないことはないはず。昔の人が自然を感じとり、歌を詠むことで自分の心と一体化させたように、私たちも自然と自分自身に真摯に向き合ってみる習慣をつければ、より研ぎ澄まされた感覚で生きることができるのではないか。(椋田侑馬)
古代の人々は現代の人々よりも音に対して敬意を払い、音と共存していたように思った。歌の中には、動物や川、山などの自然環境が描かれており、それが人々の日常生活とつながっているように感じた。現代のポップスの歌詞でも、自分たちの周りにある環境が描かれてはいるが、当時の人々による詞とは異なっている。レクチャーを受けて、現代では言葉や音に対してあまり意識していない点が多いのではないかと考えるようになった。誰かに何か伝える際には、SNSを使ってメッセージを送るし、しかも機械が音声変換や自動変換をしてくれる。また、携帯電話で音楽が聴けるようになったため、どこに行くにしてもイヤホンを持って行き、外の音をシャットダウンしてしまう。もちろん便利な時代になってありがたいけど、周りから意図せずに入ってくる音にも意識してみようと思った。(藤丸孝太郎)
これまで『万葉集』と言えば、のんびりとしたイメージがあったが、井上先生のお話を伺って当時の生活や情勢について学ぶと、歌を詠むことは単なる娯楽ではなく、知識や思想を伝える方法であり、飛鳥時代や奈良時代の人々にとって生活の必須手段だと理解できた。それを踏まえると、飛鳥時代は激動の時代で、穏やかな印象から切羽詰まったものへと変わった。「地奏」でも、参加者の飛鳥や明日香村のイメージを覆すような、驚きを含んだ内容を伝えることができれば面白いのではないか。(奥山祐)
LECTURE OUTLINE
井上さやか
2021年8月1日(日) 13:00–16:00
奈良県立万葉文化館で『万葉集』を研究している井上さやかさんから、明日香村の歴史と、『万葉集』からみたサウンドスケープについてお話しいただきました。当時の日本人は音を頼りに、どのように世界を捉えていたのか。これからプロジェクトを進めていくにあたり、重要な知識と感覚を得られる時間となりました。
1971年宮崎県生まれ、奈良県在住。博士(文学)。専門は『万葉集』を中心とした日本文学・日本文化。著書に『山部赤人と叙景』、『万葉集からみる「世界」』(共に新典社)、監修に『マンガで楽しむ古典 万葉集』、『マンガ はじめて読む 古事記と日本書紀』(共にナツメ社)、分担執筆に『飛鳥への招待』(中央公論新社)、『万葉集の基礎知識』(KADOKAWA)などがある。