REPORTS
- レクチャー
「多様な人と共に表現を捉え直す試み」
田中みゆき
2021年9月20日(月)
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)
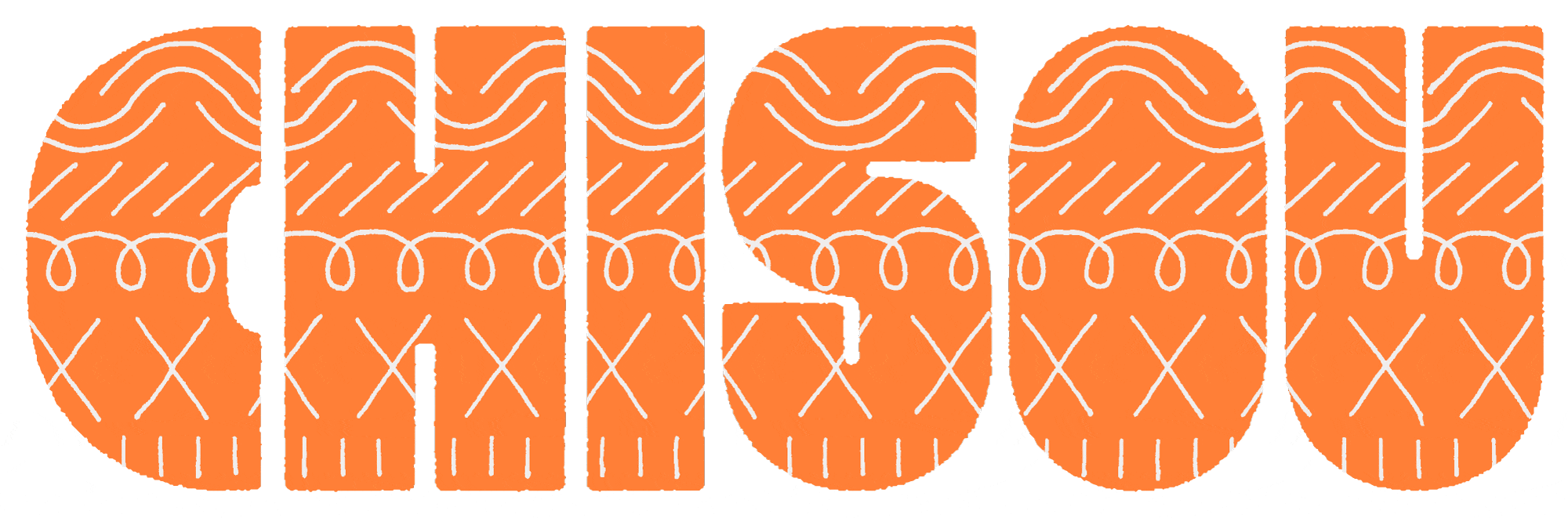
REPORTS
2021年9月20日(月)
Editor: 西尾咲子(プログラムマネージャー)

キュレーターやプロデューサーとして分野を超えて活躍する田中みゆきさんから、これまで携わってきた展覧会やパフォーマンス、ゲームなどの多様な表現活動について話を伺いました。自らの活動の指針、社会の変化の兆しを捉えて企画を立ち上げる手法、さらに、試行錯誤してつくったものを丁寧に振り返り次のステージに展開するダイナミズムについて、具体的なお話を聞くなかで「どのような姿勢でアートマネジメントを実践していくか」を改めて問い直す機会になりました。
CONTENTS
私はキュレーターやプロデューサーと名乗っていますが、どちらの肩書きでも企画するという過程においては同じことをしています。音楽や映画など、キュレーターという言葉が通用しない業界ではプロデューサーと名乗るなど、相手の都合によって使い分けています。
7、8年くらい前までは主に展覧会をつくる仕事をしていましたが、障害に関するプロジェクトに取り組むようになってからは、パフォーマンスや演劇、映画、ゲームなど、表現の幅が色々な方向へ広がっています。
展覧会と舞台芸術の自分なりの区分けについてお話しします。展覧会は、作品と対峙する空間を設計することだと考えています。動線がある場合が多いですが、固定されておらず鑑賞者は選ぶことができる。全く別の出自や世界観のものが隣に存在していて、呼応したりしなかったりする。また、鑑賞者が別々の時間軸で見ても、できる限り同じ質の体験が伝わるようにつくるのが、展覧会の基本的な特徴です。
一方で舞台芸術は、演者と観客が共有する時間を設計すること。観客に体験してほしいナラティブやストーリーがあり、時間軸に沿って設計されたものを鑑賞者は見る。ストーリーに必ずしも必要のない動作や振るまいも見る対象になっています。客席が要素の一つになっているのも特徴で、同じ演劇でも日によって違うものになるのは、観客も一緒に舞台をつくっているからです。
自らの実践の指針となるような個人的な興味が四つあり、一つ目は「作品未満の表現、コミュニケーション」です。作品になる手前では、どのように見たら良いのかが定まっておらず、どう見るかを観客がつくっていくことができる状態が好き。二つ目は「多分野の人と協働すること」。同じ業界の人だけだと、使う言葉も常識も同じで、どうしてもそこから出られないということが多々ある。別の分野の人と協働することで自分たちの常識の枠を広げるようにしています。
三つ目は「人が新しいものに触れる時の失敗も含めた態度」。どのように捉えたら良いのか悩むものに対して、自分なりの意見を持ったり行動を起こしてみたりする。それは失敗だったり、誤解だったりするかもしれないけれど、多様な意見や振るまいが起こり得る状況自体が大事。四つ目は「作者ではなく、鑑賞者が主体となるもの」。作家がどのような意図でつくったかも大事ですが、鑑賞者がどう読みとるのか、そこにもう少しできることがあるのではと考えています。
2010年に佐藤雅彦さんとつくった「“これも自分と認めざるをえない”展」では、入り口で名前を入力したり、身長や体重を測ったり、何かの形を描いたりしてから会場に入るのですが、それらのデータを活用して展示が構成されていきました。例えば、「属性のゲート」という作品では、鑑賞者は性別と年代、顔の表情で二つに分類され、顔認証の機械が判定した方のゲートだけが開く。実年齢より高く判定されても、自分と認めてそのゲートを進まざるを得ない。「指紋の池」では、現在の人口レベルだと同じ指紋の人はほぼいないという前提のもと、鑑賞者から集められた大量の指紋の池の中から、少し前に放流した自分の指紋だけが自分のもとに泳いで戻ってきます。
この展覧会を準備していた頃、指紋を偽装して日本に入国する事件が報道されました。当時は、静脈認証や虹彩認証のような技術が話題になったばかり。技術だけが発展して、自分の属性が勝手に登録されたり追跡されたりする。自覚がなくても、社会はそれを自分として認識し、独り歩きしてしまう。そんな情報で特定される属性以外のアイデンティティとは一体何なのかについて考えることをテーマにしました。
このような展覧会のつくり方を私はずっと心がけてきたように思います。「この作家の新作が見たい」というような作家主導のつくり方よりも、「今、社会では変化の兆しとして何があるか」「それを伝えるためにはどんな表現が可能か」ということを考えて展覧会をつくっています。
2009年に山中俊治さんとつくった「骨」展もそのように企画した展覧会の一つです。2007年に義足のアスリートが健常者のアスリートの記録を初めて抜いたというニュースが報じられましたが、義足のアスリートが美しく走る姿を見ていると可哀想な人とは全く思わない。人間の寿命がどんどん長くなる今、未来の骨としての可能性があるのではと思い、義足という存在に興味を持ちました。
それまで周りに障害者がいることがなく、これが私にとって最初の障害との接点でした。義足のユーザーの方々とトークイベントを行った際、普段着けている義足を何本か持参していただいたのですが、皆が思い思いに楽しんでいて、好きな布を貼って義足をカスタマイズしたり、透明なアクリルで義足をつくり変えたり。ヒールを履いたりするための義足もあって、こんなにも人の身体は色々とデザインできるのかと面白くて、約5年後に「義足のファッションショー」を企画することにつながります。
「義足のファッションショー」では、未来の人類の身体を実験的にプロトタイピングしたものとして、義足を捉えました。義足の人が歩いていると「見てはいけない」と思いがちですが、舞台なら出演者は見られることを了解しているし、むしろ見ない方が失礼。見る/見られる関係に合意があることが障害を扱う上で大事だと気づき、それ以降のパフォーマンスにつながっていきます。ファッションショーという軸に沿って、彼ら彼女らの日常の振るまいと共に、義足の種類や機能を自然な流れで見せる。当時はあまり例のない企画だったので、反響がありました。
ただ、それ以降はファッションショーをしていません。義足が並んでいる姿は壮観で、わかりやすいのですが、それで良いのだろうかとモヤっとする部分がある。難しいと感じるのは、見えないことや聞こえないことは想像の範疇にあっても、義足の身体に健常者が成り代わるのはどうしても無理で、そこにはどうしても距離がある。義足の人ってすごいねではなく、お互い良いところもあれば悪いところもあるよねとそのまま認め合えることをしていきたいと思い、その後のプロジェクトを考えています。

私のプロジェクトに共通することとして、障害のある人の存在を通して「表現の当たり前を疑う」、「鑑賞方法の選択肢を開拓する」、「知覚や感覚を拡げる」の三つがあります。例えば、この場に目の見えない人がいることで全く状況が変わる。どんな人がいるか、何をしているか、できる限り説明しますが、それって場がすごく開かれて良いなと思う。私たちが当り前と捉えていることを、あえて口に出すのです。
また「見えない人にどう伝えたら良いか」「見えている状態とは一体何なのか」について、見える人も見えない人も一緒に考える、アクセシビリティの実践もしています。アクセシビリティの一般的な意味は、障害のある人が身体的特性のために得られない情報を補助すること。私は音声ガイドの講座に通っていますが、人によって説明の仕方が全く違って、言語で説明することで少しずつその人の個性が見えるのがすごく面白いと感じます。
限られた尺の中で状態を説明する時、人によって千差万別なこと自体が「私たちは一体何を見ているのか」ということにつながっていて、「音で観るダンスのワークインプログレス」ではそれをテーマにしています。ダンスは見えていても何を見ているのかが曖昧で、基本的には言語化できない表現形態です。ダンスを言語で捉えることは不可能で、そもそも不要だと言う人もいる。誰も完璧にできないからこそ可能性が開かれているし、やる意味があると考えました。
ラジオの受信機を渡された観客は、三つのチャンネルから、それぞれ別の目線からつくられた音声ガイドを一つ選ぶ。それを聴きながら10分間のダンスを暗い状態と明るい状態で繰り返して見ます。1年目の音声ガイダンスは、一つ目がダンサー自身による解説、二つ目がアクセシビリティの観点から目の見えない人に向けて客観的に説明したもの、三つ目が能楽師の安田登さんによる神の目線からのもの。安田さんは劇場を自分の身体と捉え、ダンサーが侵入して悪さをしている、という独自のストーリーを軸に構成し、能のリズムで唄いました。隣に座っている人が違う音声を聴きながらダンスを見ていることが前提でダンスを観るのです。
「イメージとは何か」というテーマも念頭にありました。視覚的なイメージが大半を占めていますが、聴覚や触覚から想起するイメージも私たちを構成しているはず。「見えないと聴覚が鋭敏になる」と言われますが、後天的に見えなくなった人はそうではないし、その人の環境によって異なり、「足の裏の感覚が鋭くなった」など他の感覚について語る人もいます。人の感覚のキャパシティは同じで、その配分に違いがあるだけと私は思っており、色々なイメージの仕方があり得ることについて考えたかった。
隣で見ている人が全く違うものを聴いて、異なるイメージを想起している状況は、単に想像力の問題かもしれないし、その想像力を決定づけているのが身体的な違いかもしれない。そのようにダンスを見る視点の多様性を共有し、他者/自分を想像することにつながればと思いました。
ダンスの音声ガイドは日本では前例は少なく、参考になるものがないという現状があったので、1年目はイギリスから講師を招いてワークショップをしたり、映画やラジオなど他分野の音声ガイドについて学んだりしました。研究会では音声ガイドをつくるチームとダンサーと踊るチームに分かれて、実際に踊った人とテキストをつくった人がイメージを共有しながらをつくっていく。ダンスのポーズを障害当事者が触って確かめたり、実際に踊ってみたりしました。
2年目の研究会で、客観的に説明する音声ガイドを聴いた視覚障がいのある人が「何が起こっているかはわかるけど、またダンスを見たいとは思わない」と言いました。淡々と描写しても魅力がないと意味がなく、何が起こっているかを知りたくてダンスを見るわけではないことに改めて気付かされました。また、「どの音声ガイドが好きか」「どんな障害があるか」についてアンケートしたところ、視覚の状態と好みにはあまり関連性がないこともわかった。安田さんの音声ガイドは何も説明していないけど、自分で想像する余地があって面白かったと言う人もいれば、ダンサーによる音声ガイドは一緒に踊っている気になれて面白かったと言う人もいて、それぞれでした。
2年目の音声ガイドは全ての情報量が多くなり、相当複雑なものになりました。ある意味、ダンスがなくても成立する音響作品として完結してしまった。それはそれですごく面白かったと感想をいただきましたが、生のダンスから伝わるものが相対的に軽くなってしまったことに気づきました。そこで3年目では、観客も舞台に上がり、ダンサーと同じ地面を共有しながら見ることに。言葉をだいぶ減らし、ダンスから伝わる生の情報を全身で感じられる舞台づくりを心がけました。

3年間で計7つの音声ガイドをつくることを通して、「生のダンスから伝わる情報量の多さ」「想像を喚起する方法の多様性」など、様々な気づきが得られました。ダンスと音声ガイドはあえて違う人が担当していますが、そうすることで身体と声という二つの身体が舞台上に存在することになると、人間行動学者の細馬宏通さんから指摘がありました。自動ドアの音を聴くと、私たちは音として感じますが、見えない人は「あそこにドアがあり、体格の良い人が入って来た」などとダイレクトに想像し、音を存在として感じます。
また、耳だけで聴きすぎると、逆に身体を塞いでしまうことになり、「体は耳以外で聴き、目以外で観ている」ということにも気づかされました。つまり、見えることや聴こえることは身体全体での体験だということです。そして、情報としての音声ガイドだと何が起こったかは伝わってもダンスを体験したことにはならず、「共有すべきは情報よりも体験」という大事な気づきもありました。
この3年間で十分に伝えられなかったものとして、ダンスの質感がどのようなものかということがあります。言語的な限界もありますが、次はそこにアプローチしようと新作をつくっているところです。
「オーディオゲームセンター」を始めたきっかけは、アートとして行うことの限界を感じたこと。客観的な価値判断が難しいアートではなく、シンプルに体験を共有することにフォーカスを当てるような表現形態を実現したいと考えました。
1年目にゲームをつくろうと定めず取り組んでいた時、全盲のゲーム開発者の野澤幸男さんと出会いました。ビデオゲームは目が見えないとプレイできないものばかりですが、それでも彼はゲームに惹かれて、10歳の頃から独学でプログラミングを学び、音で遊べるゲームをつくっていました。ゲームではゴールが明確にあるため障害が単なる条件の一つでしかなく、勝つことやより高い点を取ることを目標にする。そうすると、お互いのできるところや良いところを見つけて、武器を最大限に使おうとするのです。そこが面白く、ゲームというプラットフォームに可能性を感じました。また、あるゲームの中で何かがこちらに向かってくる音がするのですが、人と感じる人もいれば、動物やオバケだと感じる人もいる。その面白さを残したくてあえて「ゾンビ」という言葉にしないで、「オーディオエネミー」という言い方にしたのですが、音から想像する自由さや解釈の違いの面白さを活かした体験がつくれるのではと感じたエピソードです。
2017年に「音の盲点探索ラボ」として小規模で実施し、2018年から東京ゲームショウやスパイラルなどでゲーム作品として発表し、2018年に文化庁メディア芸術祭で選出されたのをきっかけに、メディア芸術クリエイター育成支援事業で採択され、プロジェクトが徐々に大きくなっていきました。今年はソニー株式会社からお声がけいただいて、銀座ソニーパークでの「AUDIO GAME CENTER +」が実現しました。他のプロジェクトについても言えますが、最初は手弁当で試行錯誤していた試みが、徐々に依頼を受けて実施する形になり、今では自分でお金を稼いだり助成金を申請したりする必要がなく、自立して続けられるようになっています。
現在、21_21DESIGN SIGHTで、法律家の水野祐さん、コグニティブデザイナーの菅俊一さんとディレクターチームを組んで企画した「ルール?展」が開催中です。ルールと聞くと、自分と関係のないところで決められて守らされる嫌なものと思いがちですが、自ら主体となり他者と共に社会をつくるための共通言語として、ポジティブに捉えることもできるのではという観点から、アートとデザイン、舞台芸術が共存する展示空間をつくりました。
鑑賞者を信頼し、鑑賞者が作品を読み込み、自ら空間や動線などに働きかけて「自分でルールをつくった」という実感が持てるように、予め決められている会場ルールは最小限です。来場者の振るまいによりルールをどんどん変更し、新しいルールを会場に毎週貼り出します。そのルールがなぜ設定されたのかも明記されていて、どうしたらルールを変えられるかを考えることができます。
この展覧会でも障害のある人による作品を展示しています。障害とはその人固有の問題ではなく、社会や表現のルールから逸脱、あるいは除外されてきたに過ぎません。彼ら彼女らについて考えることからルールを問い直せることになるのではないかという思いがあり、これまで私がずっと取り組んできたことに通じると思っています。
個人的に関心があった、企画展「ルール?展」のディレクターを務めている田中さんのレクチャー。展覧会やパフォーマンスに、キュレーターとしてどのような視点・思考で関わっているのか、何にどのように戸惑い思考されたのかを直接お伺いできて嬉しかった。カテゴライズされた枠組みを起点に関わりを始めるのではなく、自身の興味を起点に企画を生みだしている。そのあり方を知り、固定観念で固まっていた自分の視点を柔らかくずらすことができた。コロナ禍において、田中さんが企画するイベントや展覧会も、オンラインでの実施に変更せざるを得ないことが多かったそう。でもその時に「代替としてのオンライン」ではなく、「オンラインである良さ」を活かした企画を考えたというお話に感化された。野球の試合や音楽番組をテレビで見ても楽しめるのは、オンライン用に編集され、現地では見ることのできない「寄り」や「他者のコメント(実況中継など)」が入るから。現地の観客と同じ視点で見せようとしても、受け手は楽しむことはできない。オンラインである良さをどのように使い、画面の先にいる人に届けられるかという着眼を得たので、自分自身の仕事に活かそうと思った。(中川なつみ)
「義足のファッションショー」の斬新さと、障害の通念を超えた完成度の高さに驚いたが、それを誇りに思うだけにとどまらず、そこに疑問を感じた田中さんの言葉にハッとさせられた。「オーディオゲームセンター」は、自分が子どもの頃に欲しいと思っていたゲームと近くて驚き、障害があることで、より多様な発見や開発ができる可能性を非常に感じた。「ゲームをプレイしている時は、視覚に障害がある人の方が健常者よりも圧倒的に強い」ということは、いかに社会が一部の人間のみに有利なものとして作用しているのかを知れる例だと思う。音に惹かれて、そこにある場所に意識を飛ばす経験は誰しもあるかと思うが、音にフォーカスを当てた経験は、その感覚をさらに鋭敏にすることができると思った。(奥山祐)
LECTURE OUTLINE
田中みゆき
2021年9月20日(月・祝)14:00–16:00
キュレーターやプロデューサーとして活躍している田中みゆきさんから、これまで企画に携わった展覧会やパフォーマンス、映画、ゲームなど、領域をまたぐ多様な活動について話をしていただきました。「どのように企画をつくるのか」「どのような姿勢でアートマネジメントを実践するのか」について問い直す機会となりました。
1980年大阪府生まれ、福井県育ち、神奈川県在住。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、展覧会やパフォーマンスなどカテゴリーに捉われないプロジェクトを企画。近年の企画として「音で観るダンスのワークインプログレス」(KAAT神奈川芸術劇場、2017〜2019)、映画「ナイトクルージング」(2019)、「オーディオゲームセンター」(2017〜)など。